砲兵が"God of War"や"King of Battle"なら、歩兵は「戦場の女王」(Queen of Battle)です。古今東西、戦車や飛行機のない軍隊はあっても、歩兵のない軍隊はありません。人類ン千年の技術革新をもってしても、この兵科だけは廃止できないのです。それはなぜか?答えは簡単。最も安く、その上何でもできるからです。
基本知識

歩兵はかなり万能なユニットで、敵の歩兵はもちろん、戦車・砲・塹壕・要塞の破壊、地雷や有刺鉄線の除去、偵察や待ち伏せなど、あらゆることができるユニットです。
また、徒歩移動する歩兵は、総移動力は少ないものの、ほとんどの地形を少ない移動コストで移動でき、車輌ユニットが進入できない地形(建築物など)にも進入することができます。
徒歩移動する歩兵の利点でもある、潜んでいる敵を発見する能力や自らが潜伏する(発見されにくい)能力は、経験値と密接に関連しています。
また敵ユニットを攻撃する能力は、ユニットの経験・士気値と指揮官の歩兵指揮技能値(Infantry Skill)と関連しています。いずれもこれらの値が高いほど、有能な歩兵であることを意味します。
一方、歩兵の最大の欠点は脆弱性です。歩兵は攻撃に非常に脆く、特に機関銃や火砲の攻撃にさらされると簡単に大量の抑圧をうけ、あっという間に壊滅してしまいます。
歩兵の種類
SPWAWで歩兵(Infantry:以下"Inf")として登場するユニットは、以下のようなものがあります。
- 通常歩兵(Inf)
- ライフルを主兵器とする主力歩兵です。徒歩移動が基本ですが、購入時にはトラックなど非装甲の輸送手段を備えた自動車化歩兵(Motorized Inf)、装甲車輌を備えた機械化歩兵(Mechanized Inf)などが選べます。
国籍によっては数種類の通常歩兵が登場し、例えば日本軍では、"Inf"(陸軍歩兵)の他、"SNLF"(Special Naval Landing Force;海軍陸戦隊)が登場します。 - 工兵(Engineer)
- 歩兵の中では最も用途の広いユニットです。一般に比較的重装備で、火炎放射器(Flame Thrower)や携帯爆弾(Sachel Charge)などの特殊兵器を装備するものもあります。
地雷の敷設、対戦車障害の除去、構造物の爆破など工兵にしかできないことも数多くあります。欠点は通常歩兵に比べると足が遅く価格が高いことです。 - 騎兵(Cavalry)・オートバイ兵(Motorcycle Inf)
- 馬に乗っていると想定され(馬自体は登場しない)、通常歩兵よりも移動力がある偵察用歩兵です。
一般に通常歩兵より安く、輸送手段が用意できない貧乏国むけです。類似のものとして、オートバイ兵や自転車兵があります。 - 空挺兵(Airborn Inf)
- 国籍により呼称は様々ですが、輸送機で空輸できる歩兵です。
比較的軽装ですが、ほとんどがエリート特性をもっています。 - 特殊部隊(Special Force)
- 敵戦線後方に侵入できる特殊能力をもった歩兵です。もちろんエリートに分類され、充実した装備をもっています。あらゆる歩兵の利点を兼ね備えた最強ユニットといえるでしょう。
類似ユニットとしてゲリラ部隊(Guerrilla Force)がありますが、一般にこちらは質も装備も最低です。 - 偵察兵(Recon,Scout)
- 2〜4名から構成される偵察用歩兵部隊です。ユニット分類としては、偵察(Recon)クラスになります。徒歩移動するものでも移動力が高いのが特徴で、さらに車輌を装備したものもあります。
全ユニットの中で最も索敵力は高いですが、兵員の少なさから戦闘力はほとんど皆無です。 - 狙撃兵(Sniper)
- 1名のみの狙撃専門兵です。偵察クラスに分類され、兵員の少なさから敵に発見される確率が最も低いのが特徴です。
偵察用ユニットの中では最も優秀で、エリートに分類されます。遠距離から狙撃するのは得意ですがターン当たりの射撃数が少なく、接近戦ではほとんど無力です。 - 機関銃(Machine-gun)
- 機関銃を主兵器とする歩兵で、移動力は通常歩兵に比べやや劣りますが、対歩兵殺傷力は優れています。
軽機関銃(LMG)・中機関銃(MMG)・重機関銃(HMG)に分類されます。 - 対戦車兵(Inf-AT)
- 対戦車兵器を主兵器とする歩兵です。対戦車兵器(AT)には戦車でも破壊できる米軍のバズーカや独軍のパンツァーファウストなどの強力なものや、軽装甲の車輌しか破壊できない対戦車ライフル(Atr)があります。
上記のユニットでも、国籍や年代によって部隊の質(Quality)や装備が異なることがあります。質別ではエリート(Elite)−平均(Average)−二線級(Second Line)に、装備では重装(Heavy)−中装(Medium)−軽装(Light)に分かれます。
平均的な部隊を中心として、エリート部隊では経験値(Experience)と士気値(Morale)に10%のボーナスがつき、逆に二線級部隊にはマイナス10%のペナルティがつきます。
以下では、上記のうち主に通常歩兵について説明します。他の歩兵ユニットに対してもほとんど同じことが言えますが、特殊な歩兵ユニットについては、一部当てはまらない点もあります。
部隊構成
歩兵部隊の規模は小さいものから、班(Team)−分隊(Squad)−小隊(Platoon)−中隊(Company)−大隊(Battalion)となり、おおまかに言えば、2〜5個の同規模部隊が集まると部隊規模が一つ上がります。
例えば小隊は3〜5個の分隊ユニットで構成され、同様に中隊は3〜5個の小隊で、大隊は3〜5個の中隊で構成されます。
SPWAWではほとんどの歩兵ユニットが1ユニット=1個分隊を表しますが、運用の基準単位は小隊です。つまり歩兵が移動や戦闘を行う場合は、3〜5個のユニットの集まりである小隊単位で行うことを意識する必要があります。では一般的な通常歩兵小隊はどのようなユニットで構成されているのでしょうか?
日本軍の陸戦隊を例にとると、「小隊司令部(SNLF HQ)」「歩兵分隊(SNLF Squad)」「擲弾筒(Knee Mortar)」という3種類のユニットで構成されています。小隊長と擲弾筒は1ユニットずつ、歩兵分隊は3ユニットです。
基本的にどの国の歩兵小隊もこれと同じような編成ですが、擲弾筒は日本軍独自の兵器で、ドイツやアメリカの歩兵小隊では代わりに機関銃が含まれています。
つまり、歩兵小隊は、1個の小隊司令部ユニットと3〜4個分隊ユニット、そしてこれらを支援する1〜2個の支援火器ユニット(機関銃や擲弾筒)で構成されているのです。
歩兵小隊の運用
SPWAWでは個々のユニットを使いこなす技術も大事ですが、それ以上にユニットのまとまりである「小隊」という単位で運用する技術が必要になります。歩兵小隊を構成する3つのユニットはそれぞれ異なる役割を持っているのです。
「小隊司令部」ユニットは、上級司令部と指揮下分隊との連絡中継という重要な役割を持っています。「小隊司令部」が全滅すれば、指揮下の分隊は満足に抑圧回復もできず、擲弾筒分隊は間接射撃命令を受けることもできなくなります。つまり、「小隊司令部」ユニットはできるだけ戦闘に参加させず、安全な場所にいるべきなのです。
一般に「司令部(HQ)」ユニットは、指揮下の「歩兵分隊」ユニットと比べると、兵員数も少なく装備する兵器も貧弱です。中にはピストルと手榴弾しか持っていないものもあるので注意しましょう。
一方、「歩兵分隊」ユニットは、兵員も豊富でほとんどのものはライフル・軽機関銃(LMG)・手榴弾を装備しているので中距離〜近接戦闘まで戦えます。通常は小隊の最前面に配置される歩兵戦闘の主役ですが、最前面で戦うといっても小隊司令部の3HEX(150m)以内で戦うのがセオリーです。
これは司令部との連絡を絶やさないための方法で、C&Cオンでプレイする場合は必ず守るべき原則です。これ以上離れてしまうと、小隊司令部との連絡手段は無線通信に頼ることになります。
無線の普及したドイツや大戦後期の米のような軍隊ならともかく、日本のような貧乏国の歩兵は無線装備率が最低なので、4HEX以上離れてしまうと事実上連絡手段が無いことになってしまうのです。
最後に「支援火器」ユニットは、小隊の他のユニットを支援するユニットです。そもそも支援火器とは何でしょう?
第一次大戦期、ライフルを主兵器とする歩兵同士の戦闘は膠着状態に陥ることが多く、敵歩兵を圧倒するには火砲の援護射撃に頼るしかありませんでした。しかし常に火砲の支援を得ることは難しいので、もっと簡単に運用でき圧倒的な火力を持つ機関銃が登場しました。これが後の重機関銃(HMG)です。
しかし重機関銃は射手・装弾手・運搬手など必要な兵員が多く、重たいので歩兵小隊の迅速な移動についていくことができません。そこでもっと軽い機関銃(中・汎用機関銃;MMG)が開発され、歩兵小隊ごとに配備されることになったのです。
このように歩兵小隊の火力を補う目的の兵器を、小隊支援火器と呼びます。これには機関銃などの対歩兵用兵器だけでなく対戦車兵器も含まれますが、いずれも、歩兵小隊の火力を補う役目を持った兵器なのです。
イメージとしては、敵陣地に突撃する歩兵分隊を後方から支援する、という使い方を想像してください。ということは、小隊の他の全ユニットを視界に入れられる地点に配置すべきで、さらに小隊司令部と連絡を絶やさないことも考えると、小隊司令部の後方3HEX以内に位置しておくのがベストです。
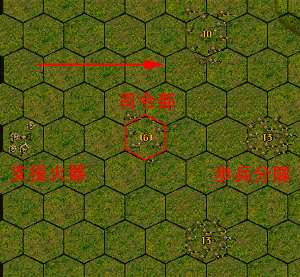
以上をまとめると、歩兵小隊の基本隊形は右図のようになります。司令部を中心として前方には指揮下の分隊、後方には支援火器を配置するという形です。
この隊形では全ユニットが司令部から3HEXの距離に配置されているので連絡不能に陥ることもなく、およそ縦横9HEX(450m四方)の範囲をカバーすることができます。
ただし、どんな状況でもこの隊形が正しいというわけではありません。支援火器は近接戦闘に弱いので司令部に隣接させておく必要があるかもしれません。
また、歩兵分隊ももっと密集すべき時もあれば、あえて司令部から4HEX以上離れるべき時もあるでしょう。そのあたりは臨機応変に対処しましょう。
状態
ユニットが移動や攻撃を行う場合、その時点でどんな状態(Status)であるかが行動の成否に大きく影響します。脆弱な歩兵はできる限りよい状態を維持しておかないとすぐに壊滅してしまうのです。歩兵を運用する場合は、そのユニットがどんな状態にいるかを常に把握しておきましょう。
歩兵の状態

ユニット上にカーソルをポイントすると、ユニットの状態や地形情報がポップアップ表示されます。また、ユニットを選択(クリックする)すると、画面下部により詳しいユニット情報が表示されます。歩兵ユニットが取りうる状態には以下のものがあります。
| 状態表示 | 意味 | 特徴 |
|---|---|---|
| "Routed" | 潰走中 | 回復するかマップ外に脱出するまで戦闘を避けようとする。 |
| "Retreated" | 退却中 | マップ外に脱出するより安全な地点まで退却したら回復しようとする。 |
| "Pinned" | 釘付け | 移動できなくなり、射撃・索敵能力が低下する。 |
| "Moving" | 移動中 | 静止状態と比較すると射撃・策敵能力が低下する。 |
| "Ready" | 行動準備 | 移動していなければ射撃命中率や敵ユニット発見率がかなり高い。 |
| "In-Cover" | 掩蔽物あり | HEX内で簡易掩蔽物を発見した状態。防御ボーナスあり。 |
| "Entrenched" | 塹壕化 | HEX内に有効な掩蔽物を擁し、最も防御効果が高い。 |
一見すればわかるように、一番上が最悪で下になるほどより良好な状態を示しています。敵から攻撃を受けると状態は悪化していきます。
「掩蔽物あり」や「塹壕化」の状態にするには、抑圧の無い状態で移動せずじっとして数ターン待つだけです。
改良状態を獲得するのに必要なターン数は、ユニットの経験値や地形によって変化しますが、ユニットの体勢(Stance)を防御(Defend)にしておく、工兵ユニットを隣接させておくなどの方法でさらに早めることができます。
ユニットの状態は、敵と交戦した場合に受ける・与える被害に大きく影響します。例えば、移動した直後の"Ready"状態のユニットが発砲しても全然被害を与えられなかった敵でも、"Entrenched"状態のユニットが発砲すると効果的に被害を与え、かつ自ユニットも被害が少なくなるのです。
つまり、敵と交戦時に発砲するユニットの優先順位は、移動したユニットよりもしていないユニット、"Ready"状態ユニットよりも"In Cover"状態のユニット、"In Cover"状態のユニットよりも"Entrenched"状態のユニットになります。この順番で発砲すれば、自軍の被害を最小限に抑え、効果的に敵を攻撃することができます。
ただし、「退却」「潰走」状態のユニットは、敵からみれば脅威ではないと想定されるので、射撃された場合の効果は半減します。また、これらの状態にあるユニットが射撃を受けると、戦意を取り戻し「釘付け」状態に戻ることがあるので注意しましょう。
被発見・被攻撃
上述したユニットの状態表示の後ろに、"*"や"#"といったマークが表示されることがあります。
この"*"マークは、
つまり、まだ敵を発見していないけれど、敵にはすでに発見されているという状態があるのです。こういう場合は、いつ敵に発砲されていてもおかしくないので、何らかの対処を施すまでは安易に移動しないほうが賢明だということが分かります。
また、運悪く敵に発砲を受けてしまった場合は、"#"マークが表示されます。このマークは、
"#"マークの方は別に意識しなくても、発砲されたらすぐに分かるので問題ないのですが、前者の"*"マークは注意していないと見逃してしまいがちです。このマークがついた直後に悲劇(!)が発生する確率は高いので、常にユニット状態表示に注意しておくようにしましょう。
移動
ユニットが移動した場合、ユニット情報には例えば"Moving 1mph"のように、移動速度が表示されます。
"MPH"は"Mile Per Hour"の略で、時速1マイルで移動していることを示しています。SPWAWは米国産なのでマイルで表示されますが、日本人としてはこの数値に1.6を掛けてKm表示に換算しましょう。"1mph"は時速約1.6kmとなり、非常にゆっくりと移動していることになります。
この移動速度表示を厳密に気にする必要はないのですが、想像力を逞しくする一つの手段としては役立ちます。そして1ターンに何HEX移動するかによって、歩兵の戦闘能力は大きく変化するのです。
移動特性
| 移動距離 | 射撃精度 | 脆弱性 | 被発見率 |
|---|---|---|---|
| 静止 | 最高 | 最低 | 最低 |
| 1HEX | ほぼ最高 | ほぼ最低 | ほぼ最低 |
| 2HEX以上 | 距離に比例して減少 | 距離に比例して増大 | 距離に比例して増大 |
SPWAWでは、1ターンの間に多く移動する=高速で移動することを意味します。
歩兵ユニットは移動距離によって、射撃精度(命中率)、脆弱性(発砲を受けた時のやられやすさ)、被発見率(見つかりやすさ)が変化します。
これらの関係をまとめると右表のようになります。
要するに、「歩兵は速く移動するほど発見されやすくなり、発砲しても命中しにくく、発砲された場合やられやすくなる」ということで、実に当たり前のルールですね。ポイントは、
具体的に脆弱性を比較した場合、2HEX以上移動した場合の脆弱性を100%とすると、静止状態の脆弱性は約20%、1HEX移動時では25%になります。静止時と1HEX移動時がほとんど変わらないのに対し、1HEX移動と2HEX以上移動した場合では大きな差があるということです。
厳密にはこの計算が成り立たないことも多いですが、できる限り移動距離を少なくすることが歩兵ユニットを長生きさせるコツであることは間違いありません。
また、歩兵に限ったことではありませんが、SPWAWでは「移動したユニットは射撃回数が減少し、射撃したユニットは移動ポイントが減る」というルールがあります。これと上記の移動特性を考慮すると、「静止状態で射撃して、その後1HEX移動する」というのが最良の方法だと言えるでしょう。
地形の利用
これまでの説明で、歩兵をやられにくくするには、"In Cover"などの良い状態を獲得し、1HEX移動を心がけることが大切だということがわかったと思います。さらに歩兵を頑強にする方法は、地形を利用することです。
SPWAWには40種類以上の地形が存在しますが、徒歩移動する歩兵はほぼ全ての地形を移動できます。また、ほとんどの歩兵ユニットの移動力は10以下ですが、大半の地形を消費移動力2〜3で通過できるのです。ちなみに地形効果表は、戦闘画面で"I"キーを押すと表示されます。
そもそも歩兵にとって何の遮蔽物もない開豁地を前進するのは非常に危険です。移動する場合はできるだけ遮蔽物を利用し、敵に見つからず戦闘に有利な地形を選ぶべきです。
遮蔽物としては、樹木や建築物、地形の高低差、さらには砲弾孔なども利用できます。最も防御効果の高い地形は、石造建物(Stone Building)、荒地(Rough)、岩場(Rocks)です。これらの地形で「塹壕化」状態をとった歩兵は最も頑強になり、間接射撃(砲撃)時の損害も半減します。
しかし、地形を利用したくても開豁地を移動するしかない!という場合も少なくありません。防御側からすれば、防御陣地は開豁地に隣接させた方が視界がよく敵歩兵を撃退しやすいのです。
こういう場合は煙幕を張って自ら遮蔽物を作り出しましょう。ただし煙幕は一時的な遮蔽物で、時間(ターン経過)がたつにつれて風下方向に広がり濃度も薄くなることを忘れずに。
移動戦術
上述した歩兵の移動に関する基本原則は、ある程度SPWAWをやったことのある人にはほとんど役にたたないかもしれません。ちょっとやってみたら、このくらいの原則は理解できるし、多くの場合、キビシー!と感じる場面でも敵に向かって前進する必要があるのが実情で、戦闘が始まれば必ず多少の犠牲は発生します。しかしちょっと移動方法を工夫するだけで、脆弱な歩兵もそう簡単には崩れなくなるのです。

敵の攻撃が予想される、あるいは実際に銃撃をうけている場合、現実でも利用されるように「相互監視」という移動戦術を使います。戦争映画なんかでも「俺が援護するからお前はあそこまで進め!」というシーンがありますね。SPWAWでもあの方法が通用するのです。
やり方は、例えば4個分隊から構成される歩兵小隊を移動させる場合には、2個分隊が前進し、他の2個分隊は静止するという方法で、これを交互に繰り返すだけです。
こうすることで、前進した2個分隊が敵の発砲を受けた場合でも、後続の2個分隊は有利な体勢で応戦できるのです。分隊が3つの場合は2−1に、5つの場合は3−2という具合に常に移動と援護の役割を分担するのがポイントです。もちろん、援護するユニットは移動するユニットを視界内に入れておく必要があるのは言うまでもありません。
1回に移動する距離は、状況に応じて決めます。敵がいるかどうかわからない場合は、数HEXずつ移動してもよいですが、敵の攻撃が激しい場合は、あくまで1HEXのみにとどめ、煙幕を併用する必要もあるでしょう。
また、相互監視する部隊の単位は、上述のように小隊内の分隊単位だけではなく、小隊単位で運用することも可能です。さらに装甲車輌を擁する歩兵ユニットならば、装甲車輌を歩兵の後方に従わせ支援火力とすることで、より効果的に援護できます。
攻撃
歩兵に適した移動方法があるように、攻撃にも歩兵に適した方法があります。敵が見えたらただバンバンと撃つ、という方法は効果的ではありません。脆弱な歩兵は遠距離で撃ち合ってもほとんどの場合負けてしまうのです。
また歩兵戦闘では、設定画面の"Reduced Squads"設定が大きく影響します。この設定をオンにすると、兵員の逃亡・義務放棄(怖くて逃げ出す・動けないなど)がシミュレートされ、総兵員数と実際に戦闘に参加する人数に差が発生します。つまり、ユニットの兵員数=戦闘に参加する兵員数にはならないのです。
敵があまりに強力な場合、自分の抑圧が高い場合、経験が低く指揮官がマヌケな場合、歩兵ユニットは満足に戦闘を行うことはできません。歩兵戦ではこの点を常に頭にいれ、能力に応じて適正な任務を与え、できるだけ戦いやすい状態を作り出すことを考える必要があります。
交戦距離
SPWAWでは、どんなユニットにも「適切な交戦距離」があります。例えば、通常歩兵が10HEX(500m)の距離で重機関銃(HMG)と撃ち合えば、まず間違いなく一方的にやられてしまいます。歩兵にとっての「適切な交戦距離」とは?
ほとんどの通常歩兵はライフルを主兵器とし、他に3つの兵器を装備しています。各兵器にはそれぞれ射程距離(Range)が決められており、基本的に射程距離以内であればその兵器を使用することができます。しかし、射程距離=「適切な交戦距離」ではありません。射程距離はあくまで、弾が飛ぶ最大の距離なのです。
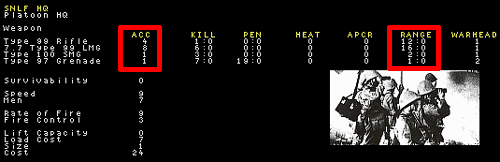
右図は日本の海軍陸戦隊(SNLF)の詳細データです。
主兵器である「九九式小銃」の射程距離は12HEX(600m)で、さらに第二兵器として、射程距離16HEX(800m)の「九九式軽機関銃」を装備しています。この第一・第二兵器は遠距離戦闘用です。
それに対し、第三・第四兵器は近接戦闘用で、短機関銃と手榴弾を装備しています。ほとんどの歩兵分隊はこのような4つの兵器を装備しています。
射程距離だけを考えると、このユニットが交戦できる最大の距離は16HEX(800m)です。ただし16HEXで交戦すると、「九九式軽機関銃」しか利用できません。他の3つの兵器は射程が足らないからです。
このように考えると、このユニットが持つ最大の火力を発揮できる交戦距離は、1HEX(50m)になります。1HEXで交戦すれば、4種類全ての兵器が利用できるのです。
なるほど確かにその通りかもしれませんが、常に1HEXで交戦するというのは不可能ですね。そのために歩兵ユニットは、近接戦闘用の第三・第四兵器とは別に、遠距離戦用の第一・第二兵器を装備しているのです。
では遠距離戦闘では何HEXで交戦すればよいのでしょうか?射程距離から言えば12HEXで交戦すれば、第一・第二兵器とも利用できますが、この距離では射撃精度は期待できません。ただ撃つだけでなくある程度の命中率が期待できる距離は?
その目安となるのが、射撃精度指標(ACC)です。この値は、非修正射撃命中率が50%となる距離をHEX単位で示しています。
上の例では「九九式小銃」のACCは"4"、「九九式軽機関銃」のACCは"8"です。したがって、「九九式軽機関銃」の命中率を50%にしたい場合は8HEX、両兵器に50%以上の命中率を期待する場合は、4HEX(200m)の距離で交戦する必要があるのです。射程距離と比べるとずいぶん短いですね。
ただし、このACCはあくまで「非修正射撃命中率が50%となる距離」であることに注意してください。実際の命中率は、交戦距離の他に、兵器性能や彼我の経験値・状態・体勢・地形など様々な要素で修正されます。つまりACCに従っても、本当に命中率が50%となるとは限らないということです。
しかし、このACCは「適切な交戦距離」を大まかに把握するには充分役立ちます。この陸戦隊ユニットで言えば、3つの交戦距離を想定できます。
最初の交戦距離は「九九式軽機関銃」のACCに合わせた8HEX(400m)。軽機の掃射を中心に、ライフルが散発的に射撃する状態です。この距離では直接的な損害は期待できませんが、ある程度の抑圧は与えることができ、前進してくる敵なら一時的に足止めできると考えられます。敵の前進を遅らせたい防御側ならこの距離で交戦を開始すべきでしょう。
二つ目は「九九式小銃」のACCに合わせた4HEX(200m)。軽機の掃射はかなり正確で、ライフルでも狙い撃ちできる状態です。この距離なら大きな抑圧を与えられ、より直接的な損害(死傷者)も期待できます。攻撃側で敵陣地を攻撃するならこの距離まで接近したいところです。防御側でもこの距離まで引きつければ、前進してくる敵に甚大な損害を与えることができるでしょう。
そして最後の交戦距離は全兵器が利用できる1HEX(50m)です。ユニットのもつ最大の火力を発揮でき命中率も抜群です。この距離で撃ち負ければ全滅を覚悟するしかありません・・・。
このように複数の交戦距離を想定することで、戦闘状況に応じた「適切な交戦距離」を導き出すことができます。つまりこのユニットの場合は、8HEX〜5HEXが警戒射撃ライン、4HEX〜2HEXが効力射撃ライン、1HEX以内が絶対死守ラインになるのです。
近接強襲
歩兵の最大の魅力は、強力な戦車や要塞さえ、一撃で破壊してしまう能力を秘めている点でしょう。もちろん遠距離で向き合ってしまえば、歩兵はなすすべもなくやられてしまいますが、敵に発見されず標的に接近し隣接してしまえば歩兵の独擅場です。
この近接強襲をマスターすれば、たった一人の歩兵が強力なティーガーを破壊することもできるのです。また、対戦車攻撃力が貧弱な日本軍などでは、最強クラスの敵戦車を破壊できるのはこの近接強襲しかない場合も多く、日本軍使いにとっては必修課程と言えるでしょう。
歩兵ユニットは、2HEX以上の距離ではライフルを発砲するなどの方法で交戦しますが、敵装甲ユニットに隣接した場合、近接強襲(Close Assault)を行うことができます。
例えば戦車に対する場合、ライフルを発砲するのではなく、敵戦車によじ登り、砲塔ハッチをこじ開けて手榴弾を投げ込むといった攻撃を行うと想定されます。近接強襲の結果には以下のようなパターンがあります。
- 近接強襲を開始し、敵戦車の破壊に成功する
- 近接強襲を開始し、敵戦車の破壊に失敗する
- 近接強襲を開始できず、普通に攻撃してしまう
- 近接強襲を開始できず、何もおきない
- 近接強襲を開始できず、むちゃくちゃ反撃される
残念ながら、最もありがちなのが5番のパターンで、最初に近接強襲が開始できるかどうかは、ユニットの質と抑圧度によって決まります。つまり、あまりに士気・経験・指揮官能力が低い場合は、近接強襲を開始することさえできないということです。
また、能力が高いユニットでも、抑圧度が高いと失敗してしまいます。したがって、近接強襲を行う直前には必ず可能な限り回復して、抑圧を低下させておくことが必要です。
とりあえず近接強襲が開始できた場合、次に敵を破壊できるか否かの判定が行われます。基準となる成功率は、強襲する歩兵部隊の戦力(人数)に基づきます。
つまり、10名で構成される分隊の強襲成功率の基準値は10%で、さらに、ユニットの士気・経験・指揮官能力などのユニットの質、抑圧度および現在の状態、ユニットが装備している兵器という要素が最終的な強襲成功率に影響します。
状態に関しては、掩蔽物あり(In-Cover)や塹壕化(Entrenched)の状態にある場合、強襲成功率は33%向上します。装備に関しては、携帯爆弾(Sachel Charge)・火炎放射器(Flame Thrower)・火炎瓶(Morotov Cocktail)の他、対戦車地雷・バズーカなどの対戦車兵器を装備していると、成功率が上昇します。
しかし逆に、そのターンで移動したユニットや、輸送車輌から降車したユニットは、強襲成功率が半減してしまいます。
白兵戦
白兵戦(Melee)も近接強襲と同じく、歩兵にしかできない戦闘方法です。白兵戦は、ライフルなどを使った通常の戦闘ではなく、銃剣突撃などの乱闘戦であると想定されます。
全ての歩兵ユニットが白兵戦を行えるわけではありません。狙撃兵(Sniper)や偵察班(Recon Team)、機関銃など一部の歩兵ユニットは白兵戦を実行できません。また、対象となる敵ユニットにも制限があり、歩兵および盤内火砲ユニットにしか白兵戦は実施できません。
白兵戦を行うには、標的となる敵と同一のHEXに位置し、キーボードの「Alt+M」キーを押すだけですが、移動ポイント(Movement Point)が残っていることが条件になります。また、抑圧度が高い場合や状態が「釘付け」「退却」「潰走」の場合は、白兵戦を実行できません。
白兵戦の手順は以下のようになります。
- 最初に、攻撃側の士気値と抑圧値のチェックが行われます。これに失敗してしまうと、最悪の場合降伏してしまい、あるいは何もできないまま臨機射撃を受けるか、白兵戦に参加する人数が半減します。
- 攻撃側が最初のチェックをパスした場合、防御側にも同様のチェックが行われ、失敗すると白兵戦参加戦力が2/3になるか、最悪の場合降伏してしまいます。
- こうしてようやく攻撃側から白兵戦が開始されます。参加人数がそのまま戦力値となりますが、手榴弾・火炎放射器・携帯爆弾を装備していると、参加人数に+1されます。
- さらに、部隊が「凶暴化する」(Go Berserk)可能性もあり、この場合も参加人数が増えたとみなされます。ちなみに、日本軍とソ連軍はこの可能性が他国よりも高く、日本軍が凶暴化するといわゆる「バンザイアタック」になり、"Banzai!Banzai!Banzai!"と表示され、バンザーイという効果音まで聞こえます!
- 攻撃側の突撃が終了すると、防御側の生き残り人数が反撃を行います。防御側も凶暴になるチャンスがあります。こうして阿鼻叫喚の効果音を聞きながら、一回の白兵戦が終了します。
白兵戦はゲーム的には非常に面白い機能ですが、実は現実と同様に、困難が多いばかりでとても効率的とはいえない戦闘方法です。
白兵戦を仕掛けるユニットが、士気・経験・指揮官能力・人数・装備の点で敵を圧倒していない限り、自ユニットにも間違いなく多くの死傷者が発生してしまいます。
しかし、この条件を満たすほど優秀な歩兵ユニットならば、わざわざ白兵戦を行う必要はなく、普通に距離を保ったまま戦闘したほうがよほど効果があるでしょう。
そもそも敵と同一HEXに進入すること自体が非常に難しいため、実際に白兵戦を行える状況は多くありません。敵と同一HEXに位置する状況といえば、視界が悪い森の中でばったり出くわした場合、敵戦線に進入しすぎて囲まれた場合、自動退却方向がたまたま敵のいるHEXだった場合(あるいはその逆)などの状況が考えられます。
それ以外の状況では、敵歩兵と隣接した時点でほぼ確実に自ユニットは発見され発砲をうけてしまい、そこからさらに(通常は移動力がなくなるので次のターンになる)敵のいるHEXに進入すると大量の攻撃を受けてしまうという点で、白兵戦をわざわざ狙って行うのは非常に難しいのです。
このように、白兵戦は有効利用しにくい機能ですが、装備が貧弱なゲリラ部隊が敵戦線奥に位置する火砲と戦う場合には有効かもしれません。
例えば日本軍の民兵(Militia)は、竹槍といわゆるチビ弾(陶製手榴弾)しか装備がなく、どちらも射程は1HEXです。どうせ隣接するなら、一気に敵にスタックしても同じと考えるかはまあ置いといて、民兵の特徴である兵員が無駄に多い(25名)という点を生かしたいところです。通常、火砲ユニットは少数の砲手しか兵員がいないので、日本軍の高い士気と兵力のみで勝負にでるのも悪くないでしょう。
障害物の除去
SPWAWに登場する障害物には、地雷(Mine)・ドラゴンティース(Doragon Teeth)・有刺鉄線(Barbed Wire)の3種類があります。
通常歩兵が除去できるのは、地雷と有刺鉄線だけで、ドラゴンティースは歩兵ユニットの中では工兵しか除去できません。工兵は他の歩兵と違い特別な機能をもっているので、別の項目で説明します。
ほとんどの歩兵ユニットが地雷と有刺鉄線を除去できますが、狙撃兵(Sniper)や機関銃(MG)など一部不可能なものもあります。ただし、偵察兵(Recon,Scout)や車輌の乗員(Crew)はこの作業を行うことができます。
これらの歩兵ユニットが障害物を除去するには、障害物が存在するHEX内に位置する必要があります。そのHEXに留まり続ける限り、毎ターン終了時に自動的に障害物が除去されます。ただし、抑圧度が高いと障害物が除去できないこともあります。
1ターンで除去できる障害物の数はおよそ1〜4個ですが、どの要素が影響するかははっきりしません。抑圧度が関係しているのは確かですが、そのほかにも人数・経験・地形などが関係しているのではないかとする説があるようです。一般に、通常歩兵が障害物を除去する速度は工兵には劣るようです。
また、地雷HEXに進入する際に、地雷が爆発してしまうことがあります。地雷が爆発する可能性があるのは、そのHEXに進入する時点および退出する時点で、その可能性は、埋設地雷数とユニットの経験値によります。
つまり、歩兵で地雷を除去するには危険が伴うということですが、地雷原は探知するのが難しいので、切羽詰った場合は安い通常歩兵を並べて前進させ爆発によって地雷のありかを発見するという、どこぞの軍隊が実際にやったような手段をとらざるを得なくなる場合もあるでしょう。
しかし、こういう生贄の役割は、キャンペーンではなるべくサポートユニットとして買った歩兵にやらせるようにしましょう。
歩兵演習キャンペーン
以上、歩兵の運用方法や特徴を説明してきましたが、文字で読むだけで理解するのは難しいですね。何事も「百聞は一見に如かず」「習うより慣れろ」です。
というわけで、日本鋼豹司令部謹製「歩兵演習キャンペーン」を用意しました。付属テキストにはここで書ききれなかった点も多く含まれているのでぜひ読んでみてください。このキャンペーンを通して歩兵の基本的な使い方をマスターしてください。
- 説明だけWeb上で見る
- まとめてダウンロードする