SPWAWでは歩兵や砲の扱いが難しいのに対し、戦車を含む車輌ユニットは比較的簡単に扱えます。目的地をクリックして移動、敵をクリックして発砲・・・直感的に操作してもそこそこ使えるでしょう。
しかし、「ガーっと移動してバンバン撃ちまくる」式の戦い方は厳しい状況では通用しません。やはりSPWAWでは、車輌ユニットにもそれなりの使い方があるのです。
"Steel Panthers"と銘打つ通りSPシリーズは戦車を主役とするゲームなので、戦車に関するルールは他の兵科に比べ細かく設定されています。以下では、史実を交えながらSPWAWの戦車運用法を詳しく説明していきます。
基本知識
SPWAWには多くの車輌ユニットが登場しますが、そもそも戦車(Tank)とは何でしょうか?まずは、その定義から説明します。
戦車の歴史

1914年から始まった第一次世界大戦では、火砲・機関銃・塹壕という要素で身動きの取れなくなった歩兵を支援する手段として戦車が登場しました。
この時点の戦車の役割は、歩兵の先頭に立ってあらゆる障害物を踏みつぶし、装甲と火力で敵の抵抗を無力化し、歩兵の敵陣突入を支援するというものでした。
初期の戦車は速度よりも超壕性能が優先された鈍重長大なものが多く、既存の火砲で破壊できたので塹壕戦で歩兵を支援する補助兵器の役割しか与えられませんでした。やがて、機動力・火力・防御力が強化されたものが登場しますが、戦車は戦争の帰趨に決定的な役割を果たすことなく第一次世界大戦は終わります。
続く1920〜30年代、各国は独自に戦車理論を発展させます。その中で異彩を放ったのがドイツでした。
WW1の敗戦国ドイツは徹底的に武装解除されて資源も人材も乏しく、質量では周辺国に太刀打ちできない。では運用面を見直すしかないというわけで、「弱者にとっての救いは堅固な防御に見いだされるに非ず。それはむしろ機動攻撃にこそあり。」という解が導かれます。
こうして防御力と火力に重点が置かれてきた戦車という兵器を、何よりも機動性を重視して攻撃的に運用する「電撃戦」理論が登場します。
SPWAWは1930年〜1949年までの戦闘を再現できますが、この20年間で戦車と戦車戦術は大きく発展します。1939年に第二次世界大戦が始まると、WW1型の戦車運用から抜けきれなかった連合諸国は一敗地にまみれ、ドイツ式運用法の正しさが証明されます。
その後、各国はドイツ式運用法を学び取り、性能面で敵戦車を凌駕しようとWW2のわずか6年間に膨大な新型戦車が投入されました。
で、長々と歴史を書いて何が言いたいかというと、「ある程度の質量の劣勢は、運用次第で挽回できる」ということであり、「SPWAWの醍醐味はこの戦車戦の歴史が再現できる点にある」ということです。
移動方式
SPWAWに登場する車輌ユニットは、移動方式により装輪式と装軌式に大別されます。装輪車輌(Wheeled)とは文字通りタイヤを履いた車輪で移動するもので、装軌車輌(Tracked)とは履帯(いわゆるキャタピラ)で移動する車輌を指します。
一般に、装輪車輌は安価で移動力が高いのが特徴です。特に整地では高速で移動できますが、不整地や悪路を移動するのは不得意です(消費移動力が大きいor移動不能)。
装軌車輌は、高価で整地移動力では装輪車輌に劣るものの、整地・不整地を問わずほとんどの地形を移動でき、建物なども倒壊させながら移動することができます。
装輪式と装軌式を良いとこ取りしたのが半装軌車輌(Half-Tracked)、いわゆるハーフトラックです。半装軌車輌は前部は車輪、後部は履帯を持ち、価格も整地・不整地移動力もそこそこ優れているのが特徴です。
半装軌式に対して、履帯のみで移動するものを全装軌式と言います。戦車には塹壕や障害物を乗り越える性能が要求されたので、当然全装軌式です。
装甲・武装
初期の戦車は、機関銃弾に耐えられるレベルの比較的薄い装甲板が取り付けられていました。後に戦車の役割が火砲や戦車との戦闘になると装甲はより厚くなり、砲弾の破片から内部乗員を守るために上面にも装甲が施されます。このように完全密閉された戦闘室を持つことが戦車の特徴です。
また、何らかの直接照準射撃できる兵器を装備していることも戦車の条件です。初期の戦車は機関銃程度の武装でしたが、後に対戦車戦闘に特化するようになると大口径の砲を装備するようになります。
構造

もともと戦車は農業用トラクターの足回りを利用して、戦闘用に装甲や武装を追加するという発想で作られた車輌でした。つまり、多くの戦車は移動を担う車台(シャシー;chassis)に戦闘用の構造物を追加するという構造になっています。
初期の戦車は前方だけに武装(機関銃や砲)を取り付けたものが多く、方向転換しない限り側背方向には攻撃できません。この欠点を補うため、前後左右に複数の武装を取り付けた戦車が登場しましたが、この方式はコストの割に効率が悪く、後に衰退していくことになります。
1917年に登場した仏ルノー製"FT17"戦車は、後の戦車のモデルとなる単一の旋回砲塔を初めて採用した戦車でした。死角を無くすには砲塔が360度旋回すれば良いという発想です。
このルノーFT17以降、戦車は車台に小さめの砲塔を載せるという構造が一般的になります。ちなみに砲塔(Turret)とは、金属で覆った銃砲座程度の意味で、搭載兵器が機関銃であろうと大砲であろうと"Turret"と言います。そして上部構造物の砲塔と対比して、車台を含めた下部構造物を車体(Hull)と言います。
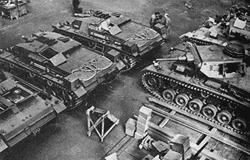
全周旋回砲塔を作るのは複雑な工程が必要でコストがかかるのが欠点でした。第二次大戦が始まると、安く簡単に大量に製造できる戦闘車輌が求められ、既存の戦車の車体に砲塔を据え付けただけの突撃砲や駆逐戦車といった種類の車輌が登場します。
このように旋回しない砲塔を固定砲塔(Fixed Turret)あるいは固定戦闘室と言います。砲塔を固定すると再び死角の問題が発生しますが、旋回砲塔よりも大口径砲が搭載でき、車高を低く抑えられたので対戦車戦闘に適していました。
何事にも例外はありますが、一般に戦車という場合は、全周旋回砲塔を持つものを指します。
戦車の種類
以上をまとめると、戦車の特徴は、全装軌式で、全周装甲と何らかの武装を持ち、旋回砲塔を備える車輌、と定義できるでしょう。SPWAWではこれらの条件を満たす戦車(Tank)は、重要や用途によってさらに以下のようなクラスに分類できます。
- 軽戦車
(Light Tank) - 偵察や対歩兵戦闘に使用される軽量・高速の戦車。手数が多い小口径砲を搭載するものが多く、多少は兵員を載せることも可能。装甲車との区別が難しいものもある。
- 中戦車
(Medium Tank) - これぞ戦車の代表格といえるクラスで、一般に有名どころの戦車はほとんどここに分類される。攻撃・防御・移動力のバランスが取れているのが特徴。一部は主力戦車(Main Battle Tank)に分類される。
- 重戦車
(Heavy Tank) - その名の通り、主力戦車より大きく攻撃・防御力に優れる反面、移動力で劣る。一対一で正面から撃ち合えば最強クラスだが、その状況を作るのが難しく使いにくい。さらに強力な超重戦車(Very Heavy Tank)クラスもある。
- 偵察戦車
(Recon Tank) - Recon能力を持つのが最大の特徴。攻撃・防御・移動力は軽戦車なみ。威力偵察に必須の一品。
- 火炎放射戦車
(Flame-Tank) - 軽戦車や中戦車の車体を流用し、火炎放射器を搭載した戦車。対ソフトスキンや近接戦には滅法強いが使いにくい。主砲を残して火炎放射器を積んだものはお得感が強いが、大抵の場合主砲威力が劣る。
- 歩兵戦車
(Infantry Tank) - 英仏独自の戦車分類。WW1以来の戦車思想に沿って歩兵戦闘の支援を主目的とする戦車。主砲が中〜大口径で短砲身であることが特徴。AP弾を持っていないものもある。歩兵の進撃速度について行ければよいというコンセプトなので移動力も低い。一般に、榴弾砲を装備した重装甲バージョンが近接支援戦車(CS-Tank)に分類される。
- 巡航戦車
(Cruiser Tank) - 英独自の戦車分類。歩兵支援よりも対戦車戦闘を重視して移動力を高めた戦車。
- 水陸両用戦車
(Amphib Tank) - 水域でも移動できる戦車。ほとんどが軽戦車レベル。
- 地雷除去戦車
(Mineclear Tank) - その名の通り地雷が除去できる戦車。車体先端に地雷除去用の鎖やドーザーを付けているので、装甲スカート値がプラスされる。類似のものに工兵戦車(Engineer Tank)がある。
- 特殊戦車
(Special Tank) - 地雷除去戦車や火炎放射戦車を除く特殊用途の戦車。空挺戦車が多いが、何が特殊かわからないものもある。
- 指揮戦車
(Command Tank) - 戦車隊指揮官が乗る無線装備が充実した戦車。一般に、移動力・煙幕弾装備率・無線装備率が高い以外はメリット無しのいわゆる雰囲気ユニット。
- 鹵獲戦車
(Captured Tank) - 敵からぶんどった代表的な戦車が分類される。オリジナルより装甲が削れていたり、各種装置能力が劣化しているので注意が必要。
- レンドリース戦車
(Lend Lease Tank) - 武器貸与法により主に米から連合諸国に供与された戦車。M3・M4系列が有名。内容的には軽戦車や中戦車がメイン。
以下の説明は、これらの戦車クラスに分類されるユニットを想定しています。他の車輌ユニットに対してもほぼ同じことが言えますが、一部当てはまらない点もあります。
状態
車輌ユニットも歩兵ユニットと同じようにさまざまな条件で状態が変化しますが、歩兵とは一部異なる点に注意して下さい。
状態変化
| 名称 | 訳 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 一般状態 | Abandoned | 放棄 | 車輌乗員が離脱(Bailed Out)した状態。 |
| Routed | 潰走 | 回復するかマップ外に脱出するまで戦闘を避けようとする。 | |
| Retreated | 退却 | マップ外に脱出するより安全な地点まで退却したら回復しようとする。 | |
| Buttoned | 釘付け | 抑圧をうけハッチを閉じた状態。移動不能になり射撃・索敵能力が低下する。 | |
| Ready | 行動準備 | 静止していれば射撃命中率や敵ユニット発見率は高くなる。 | |
| In-Cover | 掩蔽 | HEX内で簡易掩蔽物を発見した状態。索敵・射撃・防御ボーナスあり。 | |
| Entrenched | 塹壕化 | HEX内に有効な掩蔽物を擁し、最も防御効果が高い。 | |
| 特殊状態 | Hull Down | 車体隠蔽 | 車体のみ掩蔽物の陰に隠れている状態。サイズ値が4分の1になり、車体命中の可能性がなくなる。 |
車輌ユニットが取りうる状態は上表のようになります。ユニットを選択して表示される一般的な状態変化を歩兵ユニットと比べると、歩兵の釘付け状態(Pinned)の名称が"Buttoned"になり、車輌放棄状態(Abandoned)が追加されています。
車輌ユニットが砲火を受けると、車輌自体に損害がなくても乗員の抑圧値は上昇し釘付け状態になります。釘付けになった乗員は車輌のハッチを閉めてペリスコープを使うと想定されるので、もともと少ない索敵能力はさらに低下し、射撃命中率も低下してしまいます。
ただし、装甲車輌ユニットの抑圧値は歩兵の小火器(ライフル・機関銃など)による散発的な攻撃ではほとんど上昇しません。歩兵で装甲車輌の抑圧を上げたい場合は、同一ターンに集中射撃する必要があります。
車体隠蔽状態(ハルダウン)は、特定の条件が揃えば(後述)他の一般状態と同時に成立する特殊状態です。
車輌放棄
車輌ユニットが何らの損害を受けると乗員の士気チェックが行われ、失敗すると乗員が車輌から脱出してしまうことがあります。また実際には損害を受けていなくても、乗員がビビって離脱することがあります。
乗員の士気値が低いほどビビりやすく、ちょっとした銃撃で折角の装甲車輌を放棄してしまうこともあります。また、プレイヤー自らが乗員全滅の危機を回避するために乗員を一時的に脱出させる(9キー)こともできます。
脱出した乗員は放棄車輌と離れていても、抑圧低下後数ターンで再び自動的に移動し車輌に乗り込みます。プレイヤーが強制的に乗員を乗り込ませたり、異なる車輌ユニットの乗員を乗り込ませることはできません。ただし、乗員の抑圧を除去したり、乗員を放棄車輌と同一HEXに移動させることは可能です。
離脱中の乗員が損害を受けると、乗員コストのみ敵に加算されます。SPWAWでは「戦闘地域を支配している陣営のみ、戦闘が終了して敵が退却した後に放棄された敵兵器を捕獲できる」というルールがあるので、放棄車輌のコストポイントはゲーム終了時点で勝利HEXの過半数を確保している陣営に加算されます。
ハルダウン
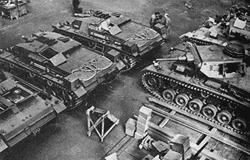
ハルダウンとは、その名の通り車体(Hull)を物陰に沈降(down)させることです。戦車の構造は車体と砲塔(Turret)とに二分できます。車体部の方が表面積は大きいのですが、高い位置にある砲塔部は車体部より敵弾が命中しやすい傾向にあります。
多くの戦車はこの点が考慮されており、砲塔部を小さくして装甲を強化する反面、表面積の大きい車体部の装甲は相対的に薄くなっています。また、車体部には戦車の命である機動力を支えるエンジンと履帯・転輪があり、この部分は戦車最大の弱点です。
戦車の中で最も脆弱な車体部を隠しつつ砲塔のみ露出させるハルダウン状態は、最も敵弾が当たりにくく、かつ全周囲を攻撃できるという点で戦車にとって最高の改良状態と言えます。戦車兵は常にこの状態をとることを意識しなければいけません。
ゲーム上でのハルダウンの効果は次の通りです。
- 命中判定に使用されるサイズ値が4分の1になる
- 車体命中の可能性は無し
- 命中する可能性があるのは砲塔のみ
砲塔にしか命中しないなら、車体よりも砲塔の装甲が薄い戦車はハルダウンした方が不利になるのでは?と思うかもしれませんが、ハルダウンすれば砲塔に命中する確率も大幅に低下するのです。
車輌ユニットは貫通弾でなくても命中するだけで、乗員が抑圧を受けたり思わぬ部分に損害を受ける可能性があります。装甲が敵弾を弾くことを期待するよりも、命中させないことが最善策です。
ハルダウン状態を獲得するか否かは、当該車輌と敵ユニットとの相対的な関係で決まります。つまり、ある敵に対してはハルダウン状態であり、同時に他の敵に対してはハルダウン状態ではないという可能性があります。具体的には、次の条件を満たせばハルダウン状態であるとみなされます。
車輌ユニットが停止しており、 - 荒地か石造建物HEXにいる場合、または
- 掩蔽状態(In-cover)にある場合、または
- 射撃してくる敵ユニットよりも高い位置にいる場合、または
- 塹壕HEX(防御戦時に配置画面で配置できる)にいる場合で、
以上の条件を満たし、かつ正面から射撃された場合。
「停止していること」という条件があるので、1HEXでも移動したターンではハルダウン状態にはなりません。ただし、掩蔽状態にあるユニットは必ず停止しているので、掩蔽状態にある車輌ユニットが正面から射撃された場合、必ずハルダウンしていることになります。
また、停止中のユニットは射撃命中率が上昇し、掩蔽状態にあるユニットはさらに命中率にボーナスがつきます。つまりハルダウン状態をとっていれば、敵に撃たれた時には命中しにくく、こちらが射撃する時には命中しやすいと良いことずくめなのです。
ハルダウンは特殊状態として扱われるので、獲得しても画面上に表示されることはありません。本当にハルダウン効果を得られているかを確認する方法はありませんが、多くの敵に対してハルダウン効果を得るためには上記の条件をできる限り満たしておきましょう。
特に「敵より高所に位置する」という条件は重要で、高地上の荒地HEXで掩蔽状態を取れば完璧です。敵車輌より高い位置から射撃すれば、トップヒット(頂部への命中)も狙える上、傾斜装甲の効果も低下するのです。
最後の条件「正面から射撃された場合」という点にも注意が必要です。例え掩蔽状態にあっても、敵に側背面を晒している場合はハルダウン効果は得られません。常に敵に正対しておくのは戦車戦の基本ですが、車輌の向きを操作するにはいくつかのテクニックがあります。
車輌の方向
歩兵ユニットはどちらを向いているかを気にする必要はほとんどありません。歩兵ユニットの向きが影響するのは、敵を発見するために周囲を見回す場合や、工兵が隣接HEXから障害物を除去・敷設する場合くらいです。
それに対し、装甲車輌ユニットの向きは戦闘結果に大きく影響します。なぜなら装甲車輌ユニットは前面・側面・背面の装甲厚が異なっており、どの部分に敵弾が命中するかによって損害の程度が大きく異なるからです。
装甲表
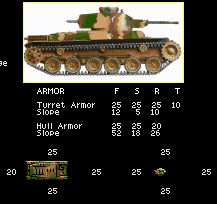
装甲車輌のユニットデータ画面を開くと、右図のような装甲表(Armor Table)が表示されます。ここでは日本軍の「九七式中戦車改」を例に、装甲表の読み方を説明します。
最上段の"ARMOR"の隣に並んでいるFSRTの文字は車輌の方向を表し、それぞれ前面(Front)、側面(Side)、背面(Rear)、上面(Top)を意味しています。
その下には、車輌の方向に対応する砲塔(Turret)の装甲厚(Armor)と傾斜角(Slope)、および車体(Hull)の装甲厚と傾斜角が数値で表示されています。一番下には車体・砲塔各面の装甲厚が図示されています。
装甲厚の単位はmmで、傾斜角は地面に垂直な場合を0度として表します。
「九七式中戦車改」は、砲塔上面の装甲厚が10mm、車体後部の装甲厚が20mmとなっており、その他の装甲厚は全て25mmと共通です。また、傾斜角を見ると、車体前面の傾斜が最も大きく52度、続いて車体背面の26度で、その他の部分はほぼ垂直と言っていいくらい傾斜角が小さいことがわかります。
例外はありますが、一般的に戦車の装甲は以下のような特徴があります。
- 車体より砲塔の方が厚い
- 前面が最も厚い
- 側面・背面が最も薄い
- 砲塔上面(頂部)装甲は皆無に等しい
また、傾斜角についても前面の傾斜が最も大きく、側背面の傾斜は小さい傾向にあります。
装甲厚と傾斜角
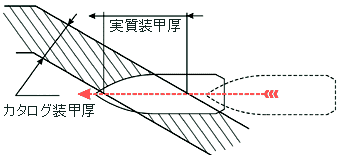
砲弾が装甲板に命中した場合、どのような角度で命中するかによって、装甲板を貫通できるかどうかが決まります。単純に言えば、装甲板に対して砲弾が垂直に命中すれば貫通力は最も高くなります。
逆に浅い角度で命中した場合は装甲板を斜めに貫通しなければならず、実質的な装甲厚が増加するので貫通力は低くなります。このため、戦車の多くは装甲に傾斜をつけているのです。
SPWAWの傾斜表示で言えば、60度の傾斜を持つ装甲は実質装甲厚が約2倍になります。つまり「九七式中戦車改」の車体前面は25mmの装甲厚ですが、実質的には約50mm近い装甲を持っていることになります。
さらに素人チックに言えば、水面に垂直に石を落とせばドボンと沈みますが、水切りの要領で水面に平行になるように石を投げれば水面を跳ねるように、砲弾も入射角が浅くなるほど跳弾(Ricochet)になる確率が高くなります。
つまり、
このように、装甲防御力は装甲厚と傾斜角をセットで考える必要あります。といっても、SPWAWの装甲貫通システムはもっともっと複雑で、装甲厚と傾斜角だけで説明できるわけではありませんが、最低限の基本としてこれだけは理解しておきましょう。
入射角と車輌方向
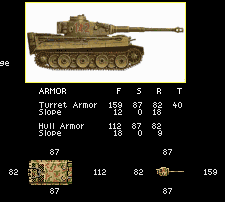
これまでの説明で、装甲厚と傾斜角が大きい面ほど敵の砲弾が貫通しにくいということがわかったと思います。これを踏まえて、装甲車輌はどういう向きに配置すれば良いかを考えましょう。ほとんどの戦車は前面装甲が最も強力なので、敵と正対する(真っすぐ正面で対峙する)のが最も有利ですね。
しかし、傾斜角が小さい装甲車輌は正対すると不利になることがあります。装甲傾斜の小さい戦車の代表格は、ドイツ軍の「ティーガー重戦車」です。ティーガーは最も装甲の薄い側背面でも80mm以上ありますが、側面装甲の傾斜角が0度(地面と垂直)でその他の装甲もほとんど垂直だという特徴があります。
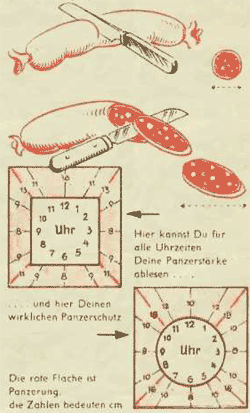
ティーガーのように装甲板の傾斜が利用できない場合でも、車体の向きを変化させることで敵砲弾の入射角を浅くすることが可能です。つまり、敵に斜めから撃たせれば、垂直な装甲板でも傾斜装甲板と同じような働きをするのです。
ティーガー戦車の乗員向け教本「ティーガー・フィーベル」では、この点を右図のように分かりやすく説明しています。ドイツ語が読めなくても何となく言いたいことはわかりますね。
曰く、ハムを真っすぐ切れば断面の直径は短いが、斜めに包丁を入れれば断面直径は長くなる。これと同様に、ティーガーの車体装甲も12時の方角から撃たれれば10cmの断面しかないが、前方斜めから撃たれれば13cmの断面になる。砲塔についても同様で・・・というわけで、入射角によって実質装甲厚が様々に変化することを説明しています。
「食事時の角度」

さらに、ティーガー・フィーベルでは続いて右図のような結論を導きます。
曰く、交戦する場合は10時半、1時半、4時半、7時半のいずれかの方向に車体前面を向けておくこと。
そして、この4つの時刻はそれぞれ朝食、昼食、コーヒーブレイク、夕食に相当することから、「食事時の角度」とはティーガーの交戦姿勢を意味するようになりました。
この「食事時の角度」の法則はSPWAWでも通用します。ティーガーに限らず装甲傾斜が小さい装甲車輌は、敵に対して車体前面を45度の角度に向けておけば入射角を浅くすることができ、正対するよりもやられにくくなるのです。
ただし、SPWAWにおいても45度が最良の角度かどうかは意見が分かれるところです。
なぜなら前方45度で対峙した場合、敵砲弾が命中するとすれば前面か側面ですが、より投影面積の大きい側面の方が命中する確率が高いと考えられるからです。一般に戦車の側面装甲は前面装甲より薄いので、できれば側面には当たって欲しくないのです。
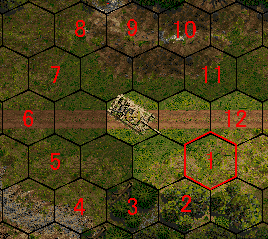
したがって、多くのプレイヤーは、
敵が12時の方向にいると想定して30度に車体を傾けるには、右図のようにユニットから2HEX離れた1時か11時の地点で右クリックしましょう。
つまりSPWAWでは、隣接HEXで右クリックすれば45度ずつ、2HEX離れた地点では30度ずつ、3HEX離れた地点では15度ずつ、車輌の方向を転換できるわけです。この仕組みを利用して常に車輌の向きを最適に保つようにしましょう。
砲塔の操作
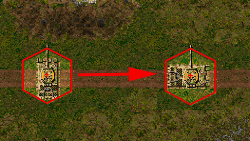
旋回砲塔(砲塔が360度回転する)を持つ車輌が移動する場合、車体の移動方向に関わらず砲塔は常に一定の方向を向いたままになります。
例えば右図のように、車体も砲塔も同じ北向きにした状態で東に移動させると、車体は東を向きますが、砲塔は北を向いたままで移動することになります。
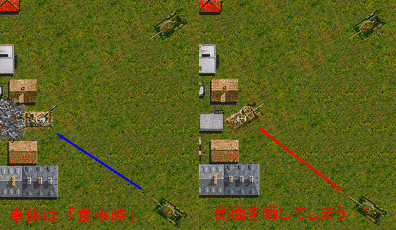
つまり旋回砲塔を持つ車輌(戦車)は車体と砲塔の向きを別個に操作することができるのです。
砲塔と車体の向きを別に操作できるメリットは、砲塔前面の強力な装甲を敵に正対させて射撃しつつ脆弱な車体は「食事時の角度」を取れる点に加えて、臨機射撃する際に砲塔だけを旋回できる点が挙げられます。
固定砲塔の車輌(突撃砲や駆逐戦車)は車体と砲塔の向きが常に同一です。固定砲塔の車輌が臨機射撃する際は車体ごと方向転換するので、複数方向から攻撃されると簡単に側背面を晒してしまうことになります(図右側)。
一方、戦車は砲塔だけを旋回させて臨機射撃するので、車体の側背面方向から攻撃されると弱いですが、あらかじめ敵の攻撃方向が予測できる状況では、旋回砲塔の特徴が有利に働きます。つまり、石造建物など敵戦車が移動しにくい地形を側背面にして交戦すれば、自分で動かさない限り側背面を晒す心配はないのです(図左側)。
砲塔の向きだけ変更して射撃するには、照準アイコン(Tキー)を使って敵ユニットに照準を定め、射撃アイコン(Fキー)を使って発砲します。すると、車体の向きは変化せず、砲塔だけ照準した敵に正対して射撃します。発砲する前にあらかじめ車体の向きを「食事時の角度」に設定しておけば、敵の反撃を受けても損害を抑えられるでしょう。
隊形
SPWAWでは車輌ユニットは1輌単位で操作できますが、運用の基本単位は歩兵と同じく小隊です。
1個小隊を構成する戦車の数は国籍によって異なりますが、ほとんどの場合は3〜5輌で構成されています。この3〜5輌の戦車が隊形を組んで行動する目的は、小隊の戦車全てを小隊長の指揮統制下に置いて常に抑圧を低く抑え、戦闘力を増進させることにあります。
戦車がどのような隊形を取るべきかは運用思想によって異なりますが、ここではWW2から現代までの代表的な隊形をいくつか紹介します。ぶっちゃけた話、隊形にこだわる必要はあまりないのですが、気分を高揚させる知識としては役に立つかもしれません。
以下では親しみを持たせるため(?)、日本軍の「四式中戦車チト」4輌を用いて隊形を図示しています。実は日本軍の戦車小隊は3輌編成ですが気にしないで下さい。
移動・攻撃隊形
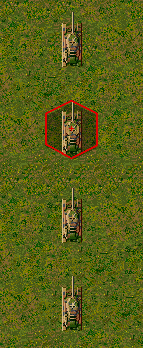
<縦隊>
縦隊(カラム・ライエ・長蛇)は、敵との遭遇が予想されない場合に使用される代表的な移動隊形で、道路などの狭い経路を素速く移動するのに適しています。
縦隊は側面へ火力を集中しやすい反面、前方への攻撃には向きません。先頭車輌の目前に遮蔽物があるだけで全車輌の前方視界が塞がれるためです。
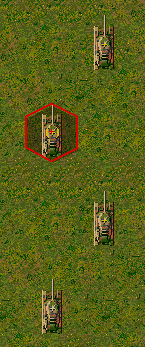
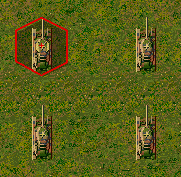
この単純な一列縦隊に改良を加えたものが二列縦隊(スタガードカラム・ドッペルライエ・衡軛)です。左側の図が独軍式の"Doppelreihe"、右側が米軍式の"staggered column"です。
二列縦隊といっても、戦車小隊がとるドッペルライエは実質的には方陣に近く、ライエより行軍速度が向上するのが特徴です。スタガードカラムは二列の戦車が互い違いに位置する点がミソで、縦隊の長さは変わらないので行軍速度は一列縦隊と変わりません。
どちらも前面・側面ともにそこそこの火力を集中でき、前列の移動を後列が監視しながら移動する点に特徴があります。といっても前列と後列は同時に移動するので、敵との遭遇が予期される状況で素速く移動するのに適しています。
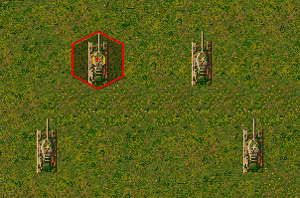
<楔隊形>
楔隊形(ウェッジ、カイル、魚鱗)は、移動・攻撃・防御のバランスが最も取れた隊形です。綺麗な楔隊形はドイツ軍戦車の突撃隊形「パンツァーカイル」として有名ですが、4輌編成の戦車小隊は右図のような隊形を取りました。
楔隊形の特徴は、前面へ最高の火力を集中できるとともに、両側面へもそこそこ撃てる点にあります。支援部隊を伴って平坦な開豁地を移動する場合には速度も出せるので、敵陣地に突入する際に多用された隊形です。
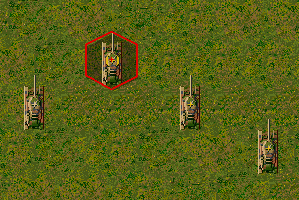
また、右図のように小隊長車がさらに前方に位置すれば、側面への火力を簡単に増加することもできます。
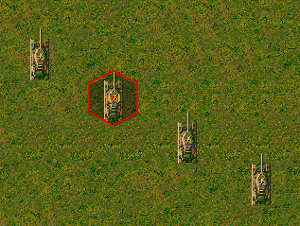
<梯隊>
楔隊形からは梯隊(エシェロン・雁行)へと移行することもできます。図は右梯隊ですが、左側に傾斜をつけた左梯隊という隊形もあります。
梯隊の利点は、片側面および前面に火力を集中できることで、敵の側面に迂回しながら交戦する場合に最適です。また、右梯隊ならば、左側にいる友軍部隊を守るのにも適しています。
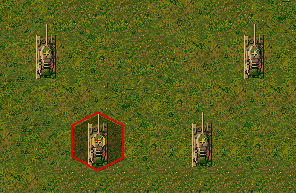
<逆楔隊形>
逆楔隊形(ヴィー・ブライトカイル・鶴翼)は楔隊形を逆さにしたもので、防御に適した隊形です。地形によって移動が制限される場合や、他からの支援が得られず小隊内で相互監視する必要がある場合に使用されます。

<横隊>
横隊(ライン・リニエ)は最も基本的な攻撃隊形で、敵陣へ突撃する際や、他の部隊の支援を受けながら危険な地域を移動する場合に使用されます。
防御隊形
以上の隊形は全て移動時の隊形ですが、次の2つの隊形は停止して使用します。
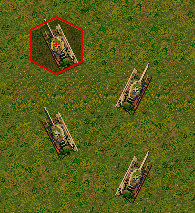
ヘリンボン(矢筈の意)は、行軍中の小隊が小休止する場合や、即時に全周防御を取る必要がある場合に使用します。道路上にいる場合は路外に出て、進行方向に対して45度の方向を向いて停止します。他のユニットが通過できるように中央部分を開けておくことで、壁役を果たします。
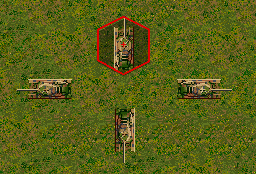
円陣(コイル・イーゲル・方円)は、いわゆるハリネズミ陣というヤツで、独立行動中の小隊が周辺防御時に使用する隊形です。小隊長車が進行方向を警戒し、その他は敵の接近が予想される経路を警戒します。
位置と間隔
上図中で選択されているユニット(赤枠)は小隊長車を表しています。
現実には、状況把握や意志決定の必要から小隊長車は常に先頭に位置することが多いようですが、先頭車輌は待ち伏せなど一番最初に攻撃を受ける最も危険な位置でもあります。したがって、SPWAWでは小隊長車は二番手か三番手に位置しておいた方が良いでしょう。
また、ユニットの間隔は常に一定ではありません。実際には地形によって移動できないHEXがあったり、敵に発見されたり攻撃を受けたりした場合は戦闘摩擦により移動ポイントが減るので、隊形に乱れがでるのはやむを得ません。
基本的には、ユニット間隔よりも相対的な位置関係を重視すべきです。また、見た目に美しい隊形を維持することにこだわるよりは、隊形が乱れてもできるだけ地形を利用しながら移動すべきです。
と言っても、ユニット同士が離れすぎると隊形をとる意味がなくなります。ユニット間隔についての基本的な原則は、
例えばドイツ軍の運用規則では、縦隊の前後の車輌間隔は、行軍中なら25m、戦闘中は150mに散開するとされています。また、楔隊形や横隊などの攻撃隊形での車輌間隔は100mとされています。
SPWAWでもこの原則は当てはまります。安全な地域では、ユニット同士を隣接あるいはスタック(〜50m)しながら密集して移動すべきです。逆に敵の攻撃が予想される地域では、一回の敵の攻撃で発生する損害を最小限に抑えると同時に、常に複数の射線を確保するために、1〜2HEX(100〜150m)の間を置いて散開しておくべきです。
SPWAWの大口径砲は着弾地点と隣接HEXに直接損害を生じさせ、航空機の大型爆弾は着弾地点から2HEXの範囲に抑圧を与えます。また、友軍ユニットが破壊されると、付近のユニットはビビって抑圧を生じることがあります。
したがって、ユニット間に2HEXの距離を取っておけば、一回の敵の攻撃が生み出すこれらの付帯損害を最小限に抑えることができます。
指揮統制
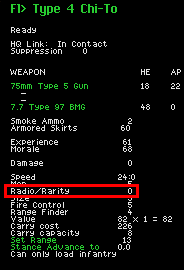
しかし、付帯損害を恐れるあまりユニット間隔を広げすぎるのも問題です。小隊は単一の移動目標に向かって移動するので、ユニットが離れすぎると隊形を保った移動が難しくなり、共通の視界がない場合は援護射撃もできません。
また、指揮統制ルールやユニット間連絡ルールをオンにしている場合、ユニット距離が離れすぎると連絡が取れなくなります。小隊長車と連絡が取れないユニットは、目標地点や体勢の変更といった命令を受け取ることができず、抑圧回復も難しくなります。
歩兵ユニットに比べると車輌ユニットの無線装備率は高いのですが、中には無線を持っていないものもあります。無線を持っていない車輌小隊が連絡を維持しておくには、小隊長車を隊形の中央に位置し、小隊ユニットはその3HEX以内に置いておいておくしかありません。つまり、無線の無い車輌小隊は密集隊形を取ることを余儀なくされるのです。
その点、ドイツ軍などは大戦初期からほぼ全車輌が無線を装備しています。このような軍隊の戦車小隊は、小隊長車からの距離を気にせず移動でき、機動力をいかして柔軟な散開行動を取れるのです。ただし、無線を装備していても常に連絡が取れるとは限りません。戦闘によって車載アンテナや無線が壊れたり、機器不調で無線が通じなかったりすることもあります。
というわけで、隊形を組む場合はユニットが無線が装備しているかどうかを確認しておきましょう。ユニット情報画面を開いて"Radio/Rarity"の項目が"0"であれば無線を装備しておらず、"1"であれば装備していることを示します。
移動
車輌ユニットも歩兵ユニットと同じく、移動するユニットは停止したユニットの支援を常に受けながら移動するのが基本です。以下では分隊単位で監視移動する方法を紹介しますが、小隊単位でも同じ方法が適用できます。
移動方法
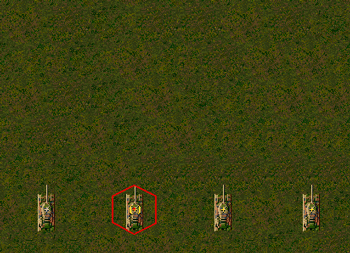
<超越躍進>
俗にいう「馬跳び(Leap Frog)」方式です。小隊を2つに分け、一方が安全な地点まで前進したら停止し、他方がさらに前方まで移動します。
図のように横隊から開始した場合は、楔と逆楔隊形を取りながら移動することになります。
2つ(以上)の班が交互に停止して監視体制を取りながら前進するので、敵と遭遇しても正確な援護射撃を加えることができます。前進速度も速いので、敵と交戦する可能性が高い場合や開豁地を移動する場合に適しています。
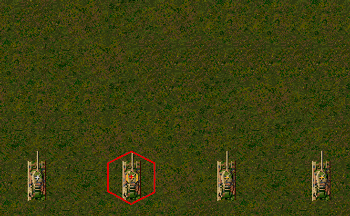
<交互躍進>
俗にいう「尺取り虫(Caterpillar)」方式で、小隊を前進班と監視班の2つに分けます。
まず前進班が前方の安全な地点まで前進し、前進班が停止してから後方の監視班が前進班の傍に移動します。監視班が監視位置についたら再び前進班が・・・という具合に繰り返します。
この方法は移動速度が遅くなりますが、足の遅い歩兵を伴う前進には向いています。また、全ユニットが密集するので火力を集中しやすく、視界の悪い地形でも敵の撃ち漏らしがなくなります。
ただし、前進班は常に先行するので監視班より危険な役割を負うことになります。適宜役割を入れ替えるか、前進班には死んでも良い程度の経験の低いユニットを使いましょう。
移動距離
一方が停止して移動中のユニットを監視する躍進移動(Bound)では、一回に前進する距離が重要です。前進ユニットと監視ユニットが離れすぎてしまうと、効果的な援護射撃ができなくなるばかりか、視界が悪い場合は前進ユニットの姿さえ見えなくなります。
ドイツ軍の教義では、常に効果的な援護体制を維持するために、前進ユニットの移動距離は監視ユニットの主砲の有効射程の半分以内に抑えるとされています。
有効射程とは一定の射撃効果が期待できる射程を指すので、SPWAWで言えば主砲のACC値を目安にすればよいでしょう。
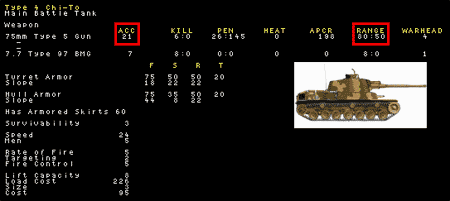
例えば、四式中戦車では主砲の最大射程は80(AP弾使用の場合は50)ですが、非修正命中率が50%になる距離を示すACC値は21です。このACC値を半分にすると10.5HEXとなり、およそ10HEX以内ならかなり精度の高い援護射撃が期待できると考えられます。
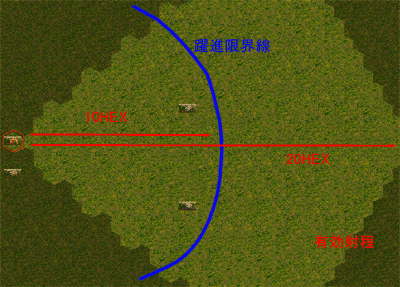
なぜ「有効射程の半分以内」なのでしょうか?具体的に説明しましょう。
四式中戦車の小隊が前進ユニットと監視ユニットとの距離を10HEX以内に保ちながら移動する場合、右図のような状況になります。
ハイライトされている範囲が監視ユニットの有効射程(ACC)で、この範囲内に敵がいる場合、監視ユニットは高い射撃精度で援護射撃できます。同時に前進ユニットも「有効射程の半分」の距離で交戦できるので、移動射撃のデメリットを考慮してもそこそこの射撃精度が維持できるのです。また、ハイライト範囲外に敵がいる場合も、射撃精度は低下しますが援護射撃は可能です。
このように、
ただし、これは視界が充分に確保できている場合の話なので、有効視界が「主砲の有効射程の半分以内」よりも短い場合や遮蔽物がある場合は、有効視界に合わせて前進距離をさらに短くする必要があるでしょう。
遮蔽物の利用
車輌ユニットは歩兵ユニットと異なり、敵の視界内で移動すればほぼ確実に発見されてしまいます。発見されるのを防ぐには、敵の視界外で移動するしかありません。
最も簡単で効果的な方法は、地形の持つ遮蔽効果を利用することです。例えば、樹木や建物HEXが密集して外部から視線が通らない場所を選んで移動すれば、少なくとも敵車輌に発見される可能性は低くなるでしょう。ただし、これらは歩兵が最も得意とする地形なので、敵歩兵の近接強襲に遭う危険は高くなります。
また、車輌ユニットは歩兵ユニットと異なり樹木や建物HEXなどを移動するのは難しいという点に注意が必要です。車輌ユニットは、樹木や建物を倒壊させながら移動することになるので、これらの地形を高速で移動すると駆動系の故障発生率が飛躍的に高くなります。
故障の可能性が高い険阻な地形はできるだけゆっくりと移動するか、樹木・建物などの外縁部の高低差を利用しましょう。
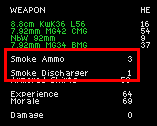
遮蔽地形が全くない場合は煙幕を利用しましょう。車輌ユニットが装備する発煙弾には2種類あります。一つは主砲から発射できるもの(Smoke Ammo)、もう一つは砲塔側面に取り付けられた専用発射筒から発射されるもの(Smoke Discharger)です。ただし、両方とも装備しているユニットもあれば、全く装備していないものもあります。

主砲から発射する発煙弾は、通常弾と同様に主砲の射程範囲内ならどこにでも射撃できます。射撃方法は煙幕直射ボタン("X"キー)を押して視界内から着弾地点を指定します。1HEX分の煙幕が張られますが、大口径砲ほど「濃い」煙幕になります。
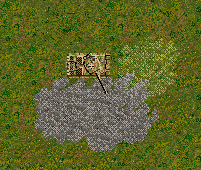
一方、スモークディスチャージャーを使用した煙幕は、砲塔の1HEX前方を中心に左右3HEXに煙幕を展開します。射撃方法は、"D"キーを押すだけです。スモークディスチャージャーは砲塔の向きを基準にするので、使用する前には砲塔の向きを調整しておきましょう。
主砲を使用する発煙弾は、視界内ならどれだけ遠距離でも即座に煙幕を張れるのが利点です。トーチカや対戦車砲の目前に煙幕を展開しておけば安全に移動できます。また、敵に見つからず側面に回り込んだり、待ち伏せを仕掛ける際にも有用です。
一方、スモークディスチャージャーは緊急避難を目的とする煙幕です。出会い頭に強力な敵と遭遇した場合は、前方3HEXを一度に覆い隠せるので後退や迂回を安全に行えます。ただし、ほとんどのユニットはスモークディスチャージャーを1回分しか持っていないので、使いどころはよく考えましょう。