SPWAWでは敵ユニットが自分の視界内にいても常に見えるわけではありません。じっと隠れている敵は視界内にいても見えない(気づかない)ことがあり、発砲されてもどこから撃っているのかわからないこともあります。そして当たり前ですが、見えない敵は撃てません。
攻撃を開始するには、まず何よりも敵を見つけ出す必要があります。どんなユニットでも敵を発見できますが、敵を発見する能力に最も優れるのが偵察ユニットで、偵察ユニットをうまく使えば「敵に見つからず敵を見つける」という理想的な状況を作ることができます。
基本知識

SPWAWでは偵察関連の用語として、"Reconnaissance(Recon,Recce)"と"Scout"という言葉が出てきます。それぞれ「偵察・索敵」「斥候」という訳を当てていますが、ゲーム上はどちらもほぼ同じ意味で使われているので、この二つの用語を厳密に区別する必要はありません。ただし、原義は若干異なるので違いを知っておくと細部が想像しやすくなるかもしれません。
オクスフォード英英辞典で調べると、"Reconnaissance"は「兵士や飛行機などを使って行う、ある地域に関する軍事目的の情報収集活動」とあります。一方"Scout"は名詞として使われる場合は「敵の配置や戦力などの情報を得るために前方に派遣される兵士や飛行機など」、動詞で使われる場合は「何かを発見・探知するためにある地域または複数の地域を捜索すること」とあります。
ゲーム中では「偵察哨戒班(Recon Patrol)」や「斥候班(Scout Team)」のように、相対的に戦闘力の小さなものに"Scout"が使用されているようです。ただし、"Scout Vehicle"を「斥候車」と訳すのは違和感があるので通例にしたがって「偵察車」と訳すように、一部の訳は厳密ではありません。
偵察ユニットの種類
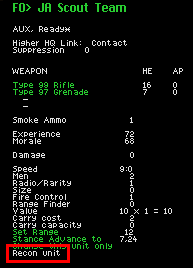
ユニットの中には、特殊能力として「偵察能力(Recon Ability)」を備えているもの(ユニットデータで右図のように"Recon Unit"と表示されるもの)が存在します。
「斥候(Scout)」、「偵察車(Scout Vehicle)」、「偵察APC(Scout APC)」、「偵察戦車(Recon Tank)」などの偵察専門クラスのユニットは全て偵察能力を持っており、これら以外にも、「狙撃兵(Sniper)」、「騎兵(Cavalry)」、「オートバイ兵(Motorcycle)」、「装甲車(Armed Car)」、「軽戦車(Light Tank)」などのクラスに分類されるユニットのほとんどが偵察能力を持っています。
偵察能力を持つユニットは歩兵系と車輌系に大別できますが、両者は索敵能力(敵を発見する能力)などの特性が異なります。
偵察歩兵の特徴
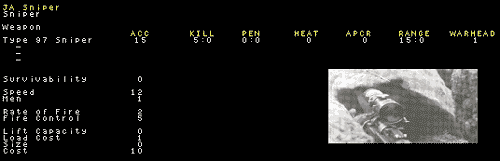
代表的な歩兵系偵察ユニットは、1名編成の狙撃兵、2名編成の斥候班、4名編成の偵察哨戒班などです。
これらは兵員数が少なくユニットサイズが0なので非常に見つかりにくいのが特徴ですが、その分戦闘力は皆無に近いので見つかってしまうと即死を覚悟しなければいけません。
移動力は通常歩兵よりも3〜4ポイント程度高く設定されています。
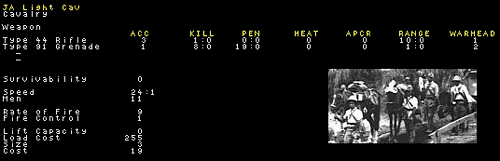
騎兵ユニットは歩兵の二倍程度の移動力を持っており、地形による移動力消費が少なく、さらに水中移動が可能な点が特徴です。
サイズが非常に大きいので車輌より見つかりやすいのが欠点ですが、険阻な地形を移動することで多少はカバーすることができます。
歩兵に比べれば兵員数や装備はややマシです。欧州諸国のスキー兵は雪原移動が得意な他は、騎兵とほぼ同じ特徴を持っています。
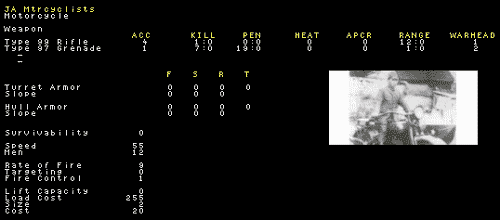
オートバイ兵は騎兵の二倍程度と全ユニット中最高レベルの移動力を誇ります。
ただし高速移動には故障の危険が伴い、歩兵や騎兵のように険阻な地形を移動するのは苦手です。
ドイツ軍のオートバイ狙撃兵は強力ですが、他国のオートバイ兵の戦闘力は騎兵とほぼ同じで、高速移動中を機関銃に狙われると一撃で全滅する危険もあります。
このほかにも特殊部隊や空挺部隊といったユニットも偵察能力を持っています。これらは兵員数も通常歩兵と変わらず、経験・装備とも優良なエリート部隊なので、最強の偵察歩兵と言えるでしょう。しかしこれらは後方潜入が主目的なので、本稿では触れません。
偵察車輌の特徴
車輌タイプの偵察ユニットは、装甲の程度によって3種類に分類できます。
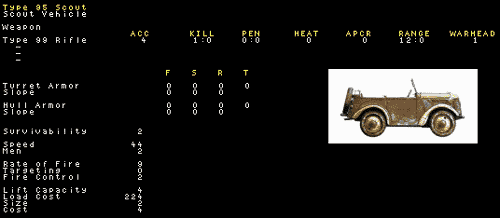
非装甲の車輌ユニットの代表格は、ジープなどの偵察車(多目的車含む)です。装輪車輌なので通過できない地形も多いですが、移動力が高いので整地なら自在に移動できます。
ただし装甲・武装とも皆無なのでライフルでも一発当たれば終わりです。値段の安さが最大のウリといえるユニットです。
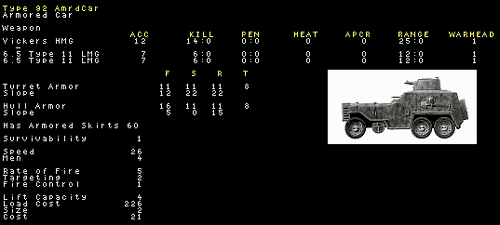
装甲車は標準的な車輌系偵察ユニットです。そこそこの装甲と機関銃を中心とする武装を備え、対歩兵なら充分に圧倒できる戦闘力を擁しています。
移動力は装輪式か装軌式かによって異なりますが、移動・攻撃・防御のバランスがとれたオールマイティな偵察ユニットと言えるでしょう。ただし、ほとんどの装甲車は積載容量がゼロなので、歩兵を乗せて運ぶことはできません。
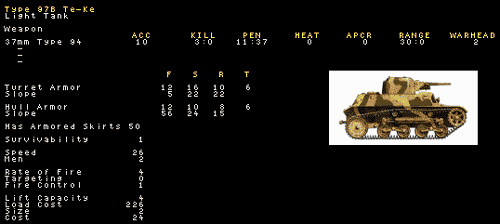
偵察戦車や軽戦車は、偵察ユニットの中で最も戦闘力のあるユニットです。仮にも戦車なので固定戦闘室と主砲を備え、装甲車程度の相手なら対装甲戦闘も行えます。
戦車の中では最も移動力があり歩兵搭載能力もあるので、偵察歩兵を乗せて運ぶことができます。といっても移動力以外では他の戦車に劣るので敬遠されがちですが、使いどころを間違えなければ充分役立つユニットです。
能力比較
偵察ユニットに求められるのは、敵の勢力圏へすばやく見つからないように移動し、隠れた敵を発見し、必要に応じて交戦する能力です。しかし、全ての点で優れたユニットは存在しません。上述した各ユニットの特徴を比較して、どのユニットがどういう点で優れているかを確認しましょう。
索敵能力
索敵能力には、偵察能力の有無とともに経験・抑圧・状態などが影響します。後者の3要素を一定として索敵能力を比較した場合、次のような関係になります。
- 偵察歩兵>通常歩兵≒偵察車輌>通常車輌
つまり、
一方、偵察車輌は通常歩兵とほぼ同じくらいの索敵能力しかないので、塹壕化した対戦車砲や対空砲などの最も発見しにくい敵を遠距離から発見するのは難しいでしょう。ちなみに通常車輌の索敵能力は劣悪で、敵歩兵と隣接しても発見できないことが多々あります。
隠密性
偵察部隊の使命は「敵に発見されずに敵を発見する」ことです。これには敵を発見する能力と同じくらい、敵に発見されない能力が必要です。
ユニットの見つかりにくさにはサイズ値で決まりますが、ゲーム中のサイズ値は経験・抑圧・状態・地形・移動速度などの要素で変動します。デフォルトのサイズ値のみでこの隠密性を比較すると、各ユニットの関係は次のようになります。
- 偵察歩兵(兵員少)>通常歩兵>オートバイ≒偵察車輌≒通常車輌>騎兵
つまり、
また、実際にはサイズのみで隠密性が決まることは少なく、敵に発見される最大の原因は移動と発砲にあります。どんなユニットでも敵の至近距離で撃ちまくれば発見されてしまいますが、サイズ値0のユニットは見つからずに数回射撃できる可能性があります。
交戦能力・機動力
では、索敵能力でも隠密性でも偵察歩兵に劣っている偵察車輌は役立たずなのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。偵察車輌が偵察歩兵に勝っている(少なくとも劣ってはいない)点は、攻撃・防御力と機動力です。
偵察部隊はその性格上、味方の先頭にたって敵勢力圏へ侵入していくので、いくら工夫しても運が悪ければ発見され、交戦する(あるいは一方的に発砲を受ける)可能性は高くなります。
偵察車輌は、車輌タイプの宿命として致命弾を食らえば一撃で壊滅する危険性はあるものの、そこそこの装甲防御力と攻撃力を備えているので、ある程度は生き残り応戦する能力があります。敵が対装甲兵器を装備していない歩兵なら、車載機銃で滅多打ちにすることさえできます(もちろん発見できればですが)。
また、敵が対戦車兵器を装備していても、致命弾さえうけなければ機動力をいかして射程外に逃れることも可能です。
交戦能力という点で比較すると、戦力の少ない偵察歩兵は言うまでも無く、戦力規模の大きい騎兵やオートバイ兵でも移動中に機銃掃射を食らうだけで大打撃を受けてしまう脆弱性をもっているため、偵察車輌には劣るといえます。
さらに、偵察車輌にとっては比較的簡単に回復できる程度の攻撃でも偵察歩兵にとっては一大事で、抑圧値が急上昇して状態悪化を招き移動不能に陥る危険性が高くなります。また、運良く移動できても、敵の射程圏から簡単に脱出するのは至難の業で、命からがら姿を隠すのが精一杯という羽目になります。
偵察方法
基本的な偵察方法は、全ての敵が一望できる地点に索敵能力の高いユニットを固定することです。例えば、塹壕化した優秀な偵察歩兵が移動も発砲もしなければ、接近されても敵に発見される可能性は低く、逆に移動・発砲する敵部隊はほぼ全て発見できるでしょう。
しかし実際には「全ての敵が一望できる地点」などというものは存在しないため、できるだけ見通しのよい複数の地点に偵察ユニットを送り込む必要があります。しかしそれでも敵が移動も発砲もしてくれなければ、発見確率は大きく減少します。
この時取りうる方法は二つ。敵に見つからないようにさらに接近するか、敵に発砲させるかです。歩兵系・車輌系偵察ユニットの特徴をいかして、それぞれに適した偵察方法をとりましょう。
隠密偵察
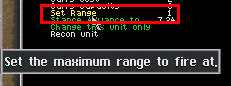
隠密偵察は、「敵に見つからないようにこっそり接近する」という最も基本的な偵察方法です。極力発見されないように移動する必要があるため、サイズが小さい少人数の偵察歩兵、つまり1名編成の狙撃兵や2名編成の斥候班に最適な偵察方法です。
隠密偵察では交戦を想定しないので、ユニット情報画面で
この方法では、敵に接近できれば発見できないユニットはありません。しかし、無用な危険を冒さず出来る限り敵と距離を置き、他のユニットには発見しづらい塹壕化した歩兵・砲・要塞ユニットを重点的に偵察するのが理想的です。
また、敵司令部や砲兵陣地の捜索にも適しています。成功のコツは、
威力(強行)偵察
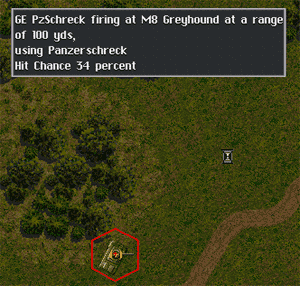
威力偵察は、あえて敵に発見されることで敵の臨機射撃を引き出し、その火点から敵ユニットの位置を発見する偵察方法です。また、見えている敵に発砲し、その反撃状況から付近にいる敵の規模や種類を知ることも目的とします。
敵の攻撃にある程度対応でき、危機が迫れば高速離脱できることを重視するので、移動力が高く攻撃・防御力も期待できる車輌タイプの偵察ユニットに適した方法です。
主要偵察対象は、サイズが大きく比較的発見しやすい車輌や移動中のユニットなどです。塹壕化した歩兵や砲を見つけるにはかなり接近しなければならず、時には近接強襲をうける覚悟も必要です。
また、敵が発砲してくれない場合はどうしようもありません。玉砕覚悟で敵に突っ込むという手段は残されていますが、偵察車輌に高度な索敵能力を求めるのはムリということは理解しておきましょう。
偵察の手順
上述の「隠密偵察」や「威力偵察」は歩兵系・車輌系ユニットの特徴を生かした基本的な偵察方法ですが、どちらも一長一短でどちらかだけを使えばうまくいくというものではありません。最上の偵察方法は両者の長所を組み合わせることです。
編成
典型的な偵察部隊の編成例には次のようなものが考えられます。
- 機動力重視(地形良)−オートバイ、装甲車、斥候班を搭載した偵察車
- 機動力重視(地形悪)−騎兵、偵察警戒班・機関銃を搭載した偵察車
- 隠密性重視−狙撃兵・機関銃・対戦車兵を搭載した偵察車
- 戦闘力重視−装甲車、斥候班を搭載した偵察車、偵察戦車or軽戦車
編成のポイントは、全体的なバランスを取りながらできるだけコンパクトにまとめることです。
また、必ずしも偵察能力を持つユニットだけで編成する必要はありません。偵察歩兵の優れた策敵能力と偵察車輌の機動力、さらに最低限の対歩兵・対装甲戦闘力は確保しておきたいところです。さらに、煙幕弾を直接射撃できる車輌があれば危急の場合に役立ちます。
しかし、あれもこれもと欲張ると肝心の戦闘部隊が貧弱になってしまいます。シナリオ状況によって異なりますが、偵察部隊に割くコストの目安としては、全購入ポイントの10〜30%程度でしょう。
しかし、予算の都合で独立運用できるほどの偵察部隊を編成するのは難しいこともあります。そういう場合は、主力部隊の戦車に狙撃兵や偵察歩兵を乗せておきましょう。これだけで戦車の索敵率は向上し、近接強襲を受ける確率も減少します。
ただし、乗車状態では偵察歩兵本来の索敵能力は発揮されません。さらに戦車に乗った歩兵は格好の的になるので、前線付近では早めに徒歩移動させましょう。
移動
偵察車などの非装甲車輌に乗っている偵察歩兵は、安全が確認できる地点で必ず降車します。降車時は発見される確率が高いので、できれば森林などの閉塞地形で降車するべきでしょう。
その後は歩兵系ユニットを前列を進み、装甲車輌は後ろから援護できる体制で前進します。
敵がいる可能性のある地域では、できる限り見つからないことを念頭において移動します。偵察ユニットは脆いので、移動する場合は以下の原則を守りましょう。
- 地形利用−できるだけ遮蔽効果の高い森や建築物、険阻な地形を移動する
- 速度制限−遮蔽地形以外では1HEX移動を徹底する
- 相互監視−複数ユニット間で移動・監視役を交互に担当する
これは歩兵系でも車輌系でも守るべき原則ですが、車輌ユニットはどれだけ注意してもまず確実に見つかってしまいます。
しかし、威力偵察の場合は敵に撃たせてナンボです。移動速度が速いほど策敵確率は低下しますが、車輌ユニットの場合は「移動速度が速いほど、敵の射撃が命中する確率は低下する」という点を利用しましょう。
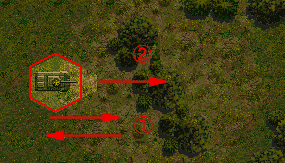
車輌ユニットは、逃げるにしても前進するにしても、最大速度で移動したほうが生き残る確率は高くなります。といっても、ただ移動できる最大距離を移動すれば良いということではありません。
障害物などを利用して安全な地点で前後移動を繰り返し、充分に速度を上げてから最終停止地点(敵から見える場所)に移動するようにしましょう。
こうすれば目的地に到達した時点で最高速度になります。当然攻撃は受けるでしょうが、命中率は大幅に低下するはずです。この移動方法は、移動目標の制限を受けず自由に移動できる偵察車輌の最大の武器です。
情報収集
偵察の具体的な目的は、敵部隊の配置・種類・規模に関する情報を収集することです。移動中は常に偵察ユニットの周辺HEXを右クリックしまくって、索敵漏れがないように心がけましょう。敵ユニットを一つでも発見したら、敵ユニット上で右クリックして次の事項を確認する必要があります。
- 種類・規模・装備・戦力
- 状態および移動中か停止中か
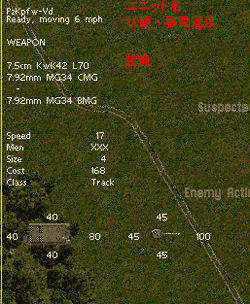
この情報を掴んだ上で「その敵は単独で存在するのか、付近にも敵がいるのか」を判断します。
例えば、発見した敵が移動中の偵察歩兵であれば、その敵は単独行動中だが後方には主力部隊が追随している可能性が高いと判断できるでしょう。また、塹壕化した歩兵分隊であれば、歩兵陣地の一部である可能性が高く、付近には同一小隊の残りがいると判断できるでしょう。同様に、対戦車砲であれば付近にはそれを援護する機関銃が、移動中の戦車であれば随伴歩兵がいる可能性も高いと判断できます。
このように、典型的な用兵パターンから見えていない敵を想定することで、その後の偵察活動が効率的になり不用意に敵と遭遇することも回避できるので、結果的には偵察部隊を長生きさせることに繋がります。しかし、対人戦ではここに敵の欺瞞工作の余地があるのも事実で、相手プレイヤーの用兵を読み合う必要もあります。
これらの敵情を把握できたら、前進・迂回して別の偵察地点に向かうか、その場に留まって監視を続けるか、後退あるいは交戦するかを判断します。
基本的に隠密偵察の場合は偵察活動を継続します。隠密偵察では敵戦線後方まで侵入して敵司令部や砲兵陣地を発見するのが最終目標です。敵が前進してくることが予想される場合は、理想的な偵察地点に留まって監視するのも効果的でしょう。
威力偵察の場合は、敵を発見した時点ですでに臨機射撃を受けている可能性が高いでしょう。敵戦力の分析結果から判断して、迂回・後退するか交戦するかを決定します。
交戦
偵察部隊が交戦する場合は二通りの可能性が考えられます。一つは敵を先に発見し情報収集を行った後で、勝てると判断して交戦を開始する場合です。
この場合は、交戦開始後に予想外の敵がいた!ということがないように充分な偵察を心がけ、後続部隊が到着するまで時間を稼ぐだけなのか、偵察部隊だけで敵を一掃するつもりなのかを決めておきましょう。
偵察部隊が交戦する場合は、できるだけ自軍の全容を見せないようにすることが重要です。複数の敵を相手にする場合は、全ての敵に抑圧を与えた後で各個撃破すると自軍の姿を見られにくくなります。
交戦が始まるもう一つの可能性は、敵の臨機射撃を受けた場合です。運良く射撃してきた敵を発見できた場合は威力偵察成功です。しかし実際に最も多いのは、「発砲を受けたものの敵が見えない」というパターンです。とりあえず発砲の瞬間表示されるポップアップを頼りに、発砲された兵器名称と発砲ユニットの種類を推測しましょう。慣れれば射撃音だけで判断することも可能です。
抵抗できそうな敵なら、装甲車輌が正面で抵抗する間に偵察歩兵を迂回接近させ敵の発見に努めます。可能なら砲撃するのも効果的です。砲撃により隠れている敵の抑圧値が上昇すると、発見確率が上昇することを覚えておきましょう。
交戦回避
偵察ユニットは価格以上の価値があるので、運悪く強力な敵に発見・射撃された場合はできるだけ戦闘を回避しましょう。特にゲーム序盤で自軍の眼を奪われてしまうのはどう考えても得策ではありません。
敵の射界から逃れるには地形を活用するのが基本ですが、遮蔽物が利用できない場合は煙幕を使用します。
通常、歩兵ユニットは発煙手榴弾を何発が装備しているので、一時的に後退・迂回する場合は役立ちます。抑圧が高すぎる場合は煙幕弾も発射できませんが、それほど抑圧が高くない場合は煙幕弾を発射してから回復作業を行った方が回復成功率が高くなります。
これは敵の視界から逃れることで兵士の緊張が緩和されるためです。また、敵の追撃をかわすため、煙幕発射後はその地点から移動しておくことも重要です。
歩兵の煙幕弾は隣接HEXにしか展開できないので、開豁地を迂回せざるを得ない場合などは役に立ちません。火砲の間接射撃で煙幕弾を張るという手はありますが、遅延時間0.2以内で砲撃させるのは難しいことが多いでしょう。その点直接射撃できる盤内砲なら問題ありませんが、盤内砲の多くは移動力に難があるので危急の場合は役に立ちません。
こういう場合は煙幕弾を直射できる車輌が役立ちます。離れた地点から敵の目前に煙幕弾をZ射撃すれば、敵の交戦能力を一時的に麻痺させることができます。
煙幕弾(Smoke Discharger;煙幕投擲器ではない)を装備している車輌は多くはありませんが、偵察戦車・指揮戦車・主力戦車・自走砲・突撃砲などは装備していることが多いようです。

発見した敵が強力な対戦車兵器を擁した大部隊で、煙幕も遮蔽物もなく、一歩でも動けば破壊される運命にあると判断した場合は、最後の手段として"9"キーを押すという選択肢もあります。
こうすれば車輌から乗員(Crew)が退避(Bail out)し、車輌は放棄(Abandoned)されたものとして扱われます。放棄車輌はAIの攻撃対象にならない上、乗員は当然歩兵タイプなので、それ以上移動しなければ敵の視界から突然消え、即席偵察兵として活躍させることも可能です。
退避した乗員は数ターン抑圧がない状態にあれば、再び車輌に乗り込み戦闘に復帰しますが、敵の強固な要塞の前で忘れた頃にいきなり復帰されると困るので、退避乗員の動向には常に注意しておきましょう。
対偵察戦
偵察部隊には、敵を発見するとともに敵の偵察活動を阻害する役割もあります。原則として偵察部隊は積極的に交戦すべきではありませんが、敵の偵察部隊を発見した場合だけは別で、確実に撃滅しておかなければいけません。
最も重要な目標は敵の偵察歩兵です。戦闘序盤で敵の偵察歩兵を全滅させれば、その後の戦闘の主導権を握ることが出来ます。
しかし偵察歩兵ユニットを発見するのは容易ではありません。特に敵が移動していない場合は、こちらの偵察歩兵でも発見は難しいでしょう。また、運良く敵の偵察歩兵を発見できたとしても、偵察歩兵同士が撃ち合うだけでは全滅させるのは至難の業です。
防御戦や遭遇戦で敵の偵察歩兵を狩る基本的な方法は、発見を担当する偵察歩兵と壊滅を担当する装甲車や機関銃からなる対偵察チームを最前線に配置することです。敵の偵察歩兵を発見する任務には最も優秀なユニットを当てるべきで、経験値ボーナスがある"Elite Recon"扱いの狙撃兵が適しています。
狙撃兵が発見次第、機関銃が抑圧を上げておきましょう。これだけでも敵の索敵能力は大きく低下し移動もできなくなるはずです。可能であれば装甲車が直接トドメを刺しにいくか、火砲で砲撃しておきます。偵察歩兵は兵員数が少ないので、火砲の砲撃(直射含む)には非常に弱いのです。
敵を壊滅できなかった場合に重要なのは、地形か煙幕を利用してこちらの姿を隠すことです。敵に姿を見せたままターンを終了するのは危険です。一時的にどれだけピヨっていても、敵のターンで復活したり増援が登場する可能性はあるのです。
敵の偵察活動を阻害するという目標を達成するには、必ずしも敵の偵察ユニットを全滅させる必要はありません。要はこちらの配置や戦力を敵に見せなければよいのです。常に車輌や火砲の煙幕弾を利用して敵の視界を制限するのが基本です。
敵が移動せず発見できない場合でも、怪しい地点の周辺を煙幕で塞げば敵に移動を強いることができるかもしれません。
偵察部隊の運用
偵察部隊には索敵以外にも多くの用途が考えられます。偵察部隊は他のユニットのように、マップ端に移動目標を設定しマップの横軸を直線的に前進しながら敵を掃討するといった硬直した運用をすべきではありません。
前進・後退・迂回という行動が自由にできるのが偵察ユニットのメリットです。C&Cをオンにしている場合こそ、「偵察ユニットは移動目標を無視して自由に移動できる」という特長を最大限に利用しましょう。
側面援護
ゲーム中盤から後半にかけて両軍の全面衝突が始まると、偵察部隊による索敵の必要性は徐々に薄れていきます。互いが激しく移動や射撃を繰り返すようになれば、通常歩兵だけでも充分敵を発見できるでしょう。
もちろん、偵察部隊には敵陣奥地の司令部や砲兵陣地を発見するという任務が残されていますが、両軍が衝突する真っ只中にいる必要はなく、偵察部隊が激戦に巻き込まれるような状況は避けなければいけません。
つまり、偵察部隊は両軍主力の交戦が開始される直前に、安全な主力側面に位置しておく必要があります。敵の手薄な側面を前進すればよりスムーズかつ安全に偵察が行え、自軍主力の側面や後方に回り込もうとする敵の別働隊や偵察部隊を早期警戒できます。弱小戦力でも側面に配置しておけば、主力部隊は安心して前だけをみて戦えるのです。
後方警戒・予備戦力
偵察部隊は、敵の潜入部隊(特殊部隊やゲリラ)や空挺部隊から自軍後方地域を守る後方警戒部隊としても役立ちます。進撃戦や遭遇戦では敵の大規模な後方進出は想定しにくいので、4名編成の偵察哨戒班くらいで間に合うかもしれませんが、オートバイや装甲車などの機動力を持つ偵察ユニットを後方に待機させておくことは防御戦では特に重要です。
このような偵察部隊は予備戦力としても利用できるので、自軍戦線に開いた穴を一時的に埋めたり、弱い箇所を補強したりするのに役立ちます。また進撃戦でも予備戦力をゲーム中盤まで温存しておくことで、ここ一番で主力部隊と協調して敵の側面を突いたり、敵戦線の弱った部分に突入して一気に敵後方に進出するといった用途にも使えます。
偵察部隊は移動目標に制限されず移動できるので、危機が迫った地点に急行する必要のある予備戦力として最適なのです。戦闘力では通常の戦車より劣りますが、偵察歩兵や機関銃・対戦車ライフル歩兵などと組み合わせれば、どんな敵に対しても臨機応変に対処できるでしょう。
防御戦
防御戦では偵察部隊はどのように運用すべきでしょうか?基本は小規模の偵察歩兵を見通しの良い地点に前哨として固定し、敵の進撃状況を監視することでしょう。この時、ある程度の縦深をとって複数の偵察ユニットを配置しておけば、敵の位置を正確に掴みやすくなります。
また、監視役にFOユニットを使えば、前進してくる敵に効果的な砲撃を加えられるでしょう。FOは偵察能力を備えており兵員も少なく優秀な偵察ユニットですが、値段が高いのがやや難点です。
もう少し積極的な運用法としては、主要防御線の前方に機関銃や対戦車ライフル兵を伴った偵察歩兵を配置し、小規模な抵抗線(ピケライン)を張る方法もあります。視界さえ確保できれば偵察歩兵の索敵範囲は通常歩兵より大きいので、少ないユニットでも大きな範囲をカバーできるという利点があります。
ただし、大部隊が突っ込んできた場合には抵抗しようが無いので、なるべく敵が来そうにないマップの両端や地形の険阻な地点に配置するようにし、突破された場合に備えて後方には予備戦力を用意しておきましょう。
低視界戦闘
偵察ユニットは遠距離から敵を発見できる点に特長があります。しかし、悪天候で有効視界が低い場合や地形により視界が極度に制限されるジャングル戦や市街戦などでは、この利点が生かせません。
このような低視界シナリオでは歩兵同士の接近戦が主体となるため、偵察歩兵といえども発見される危険はかなり高く、車輌ユニットは近接強襲を受ける危険が高くなります。
低視界シナリオでは戦線後方への浸透も容易になるので索敵の重要性は高まりますが、視界が良い時のように損害を出さずに偵察するのは困難です。
低視界状況での偵察部隊の基本的な運用法は、小規模偵察歩兵を等間隔で横一線に並べて「散兵線」を構築することです。2HEX間隔で偵察歩兵を配置できれば、敵の浸透をほぼ完全に探知できます。
ただし、敵浸透部隊と遭遇すれば損害を受けるのは避けられません。したがって、散兵線を構築するのは最も安い斥候班に任せるべきでしょう。また、散兵線の後方には偵察車輌を待機させ必要に応じて支援に向かわせます。
オートバイや騎兵は手榴弾を装備しているので接近戦も戦えますが、万全の状態の歩兵が相手では分が悪いでしょう。攻撃力で劣るこれらのユニットは、歩兵の援護役に徹しましょう。
つまり、自軍歩兵と戦って釘付け・退却・潰走状態になった敵を掃討する役目を負うのです。ターン開始時には自軍歩兵の後方で待機しておき、敵歩兵が弱体化したら後方から飛び出して掃討し、ターン終了時には再び歩兵の後ろに戻っておきましょう。